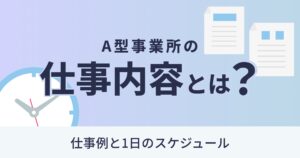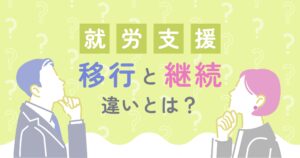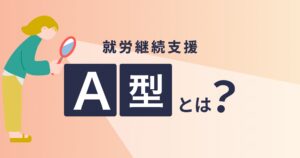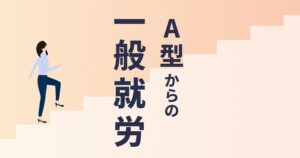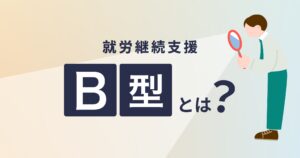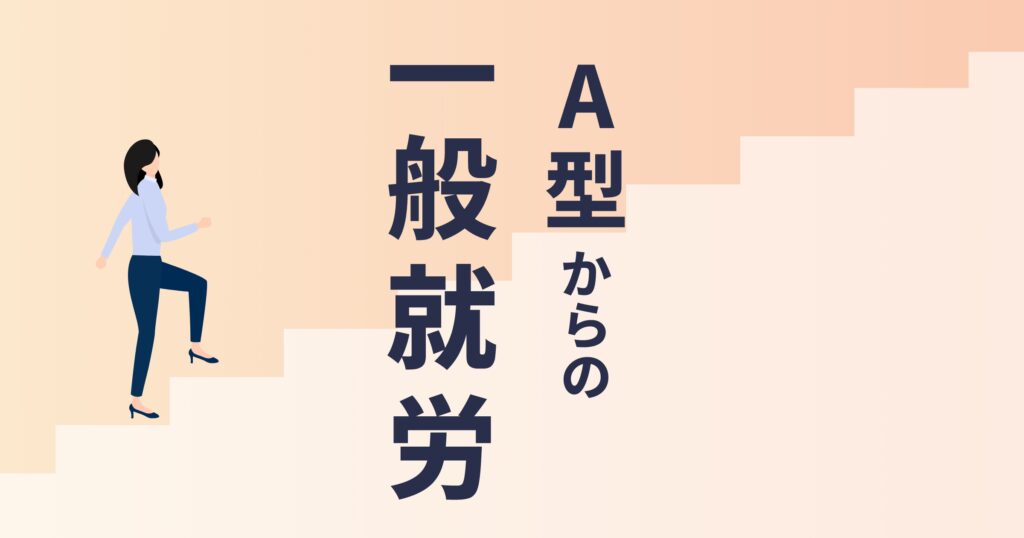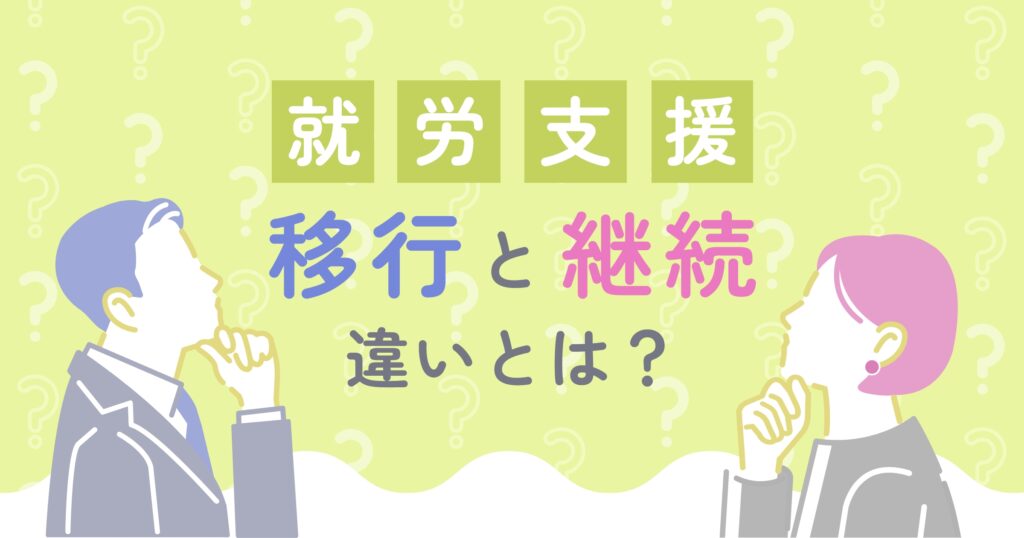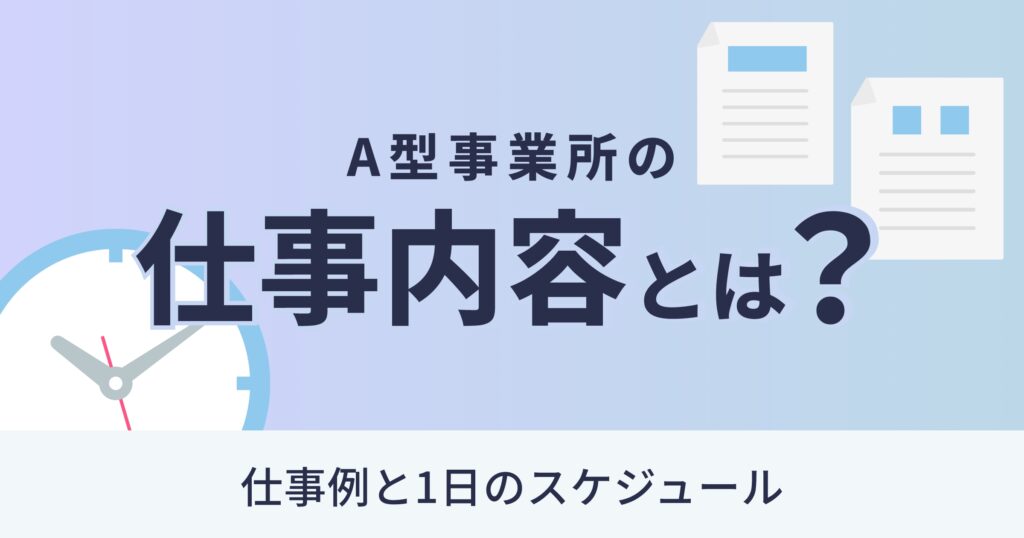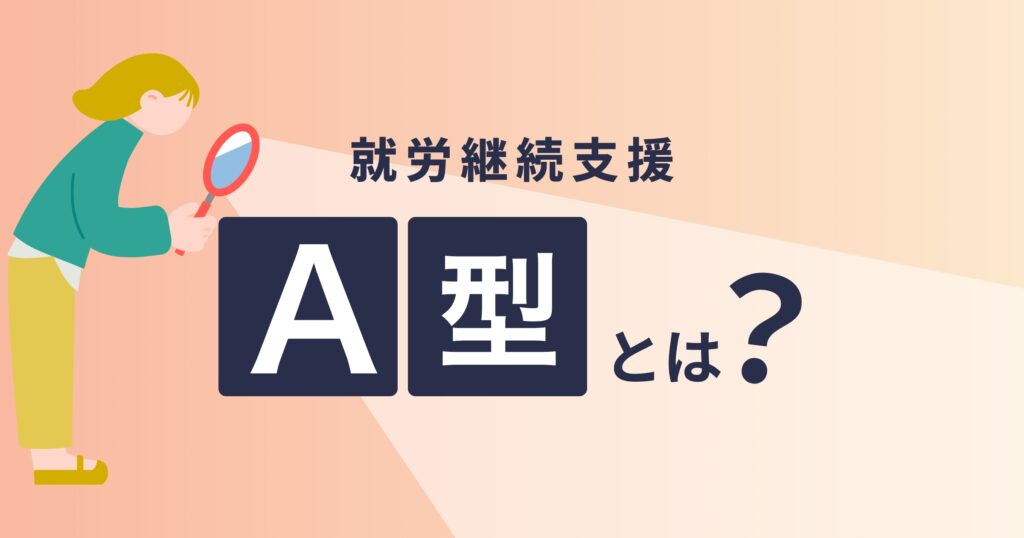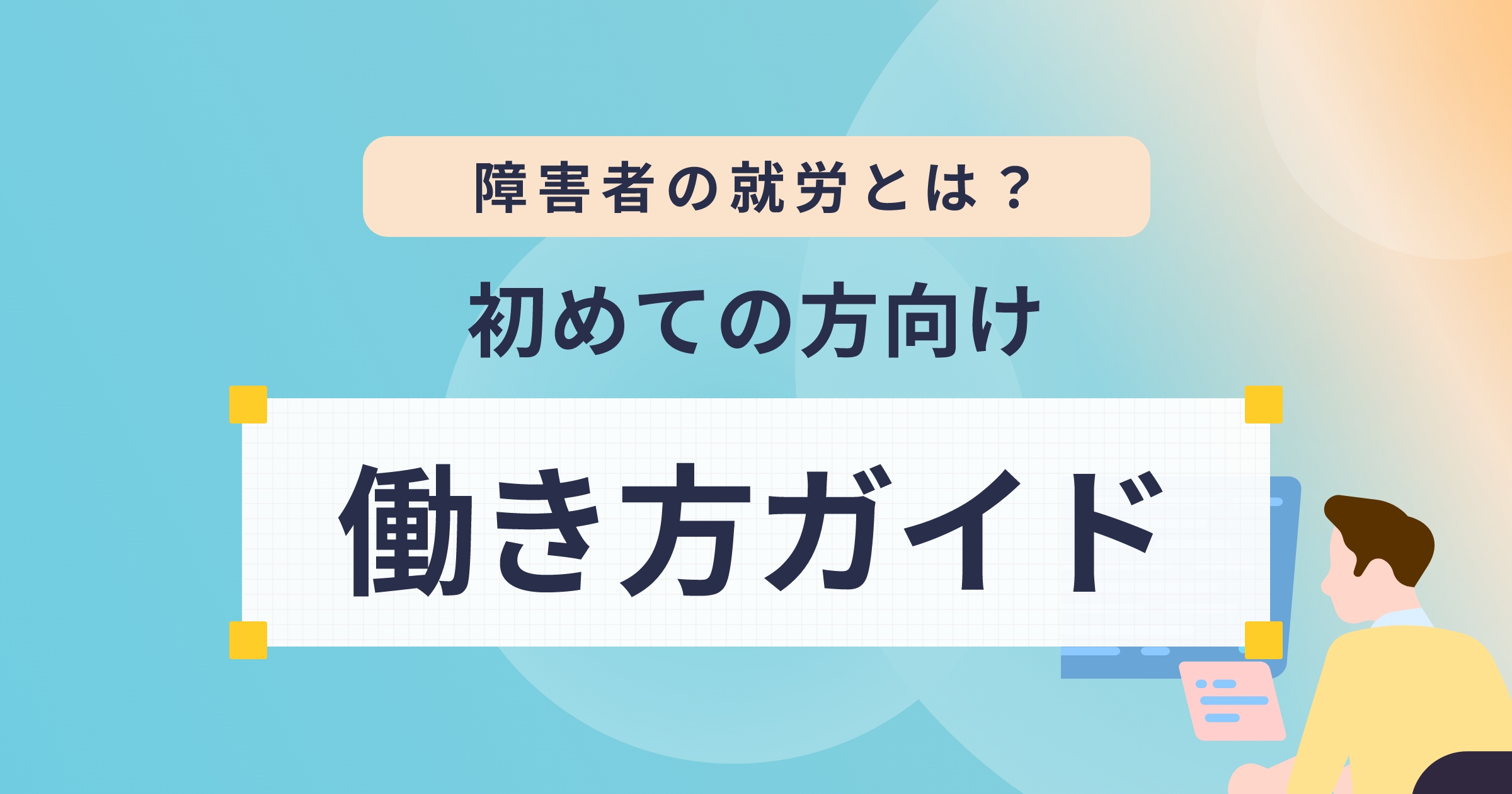
障害者の就労とは?初めての方向け 就職の流れ・支援制度・働き方ガイド
この記事の監修者

佐井 万輝
生活支援員
高校卒業後に福祉に携わる機会があり、就労における福祉的な視点を獲得したいと考え福祉の大学に入学。卒業後はピアサポートに近い支援を行っている人材派遣会社に興味を持ち就職。その後は障害者に対して直接支援をしている就労継続支援の分野を実際に経験したいと思ったこと、また利用者の状況に応じ……
障害者の就労とはー働くことの意義や昨今の雇用状況について

障害のある方にとって、働くことは経済的な自立を可能にするだけでなく社会参加を促進し、自己肯定感を高める上で重要な意味を持ちます。仕事を通じて社会とのつながりを感じ、自身の能力を発揮することは、充実した生活につながります。
昨今、障害者の雇用は着実に進んでいます。厚生労働省の発表によると、民間企業における障害者の雇用者数・実雇用率は増加傾向にあり、令和6年度の集計では過去最高記録を更新しました。これに伴い、企業に義務付けられている障害者の雇用割合(法定雇用率)も段階的に引き上げられており、企業側は今後さらに障害者雇用への理解を深め、積極的に取り組む姿勢が求められています。
※参考:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
障害者の働き方の種類
障害のある方の働き方には、「一般就労」「障害者雇用枠での就労」「福祉サービスを利用した働き方」の3種類があります。
一般就労
一般就労とは、障害のない方と同じように一般企業に就職して働く形態を指します。職種や働き方に制限は少なく、自身の能力や経験を活かしてキャリアアップを目指すことも可能です。ただし企業からの特別な配慮が少ない場合があるため、自身の障害特性を理解し、自己管理能力が求められる働き方と言えます。障害があることを開示するか否かは、自身で選択できます。
障害者雇用枠での就労
障害者雇用枠での就労は、障害者手帳を持つ方を対象とした求人に応募し、企業からの配慮を受けながら働く形態です。企業は障害者の法定雇用率達成のため、障害者雇用に積極的であり、障害特性に応じた業務内容や労働時間の調整、職場環境の整備など様々な配慮が期待できます。
障害者雇用を選択すると、一般の求人に比べて選べる職種が少ないという特徴があります。しかし障害者雇用に積極的な企業には大企業が多く、長期的に安心して働ける職場に就職しやすいという利点があります。
障害福祉サービスを利用した働き方
福祉サービスを利用した働き方には、主に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の3つがあります。これらのサービスは、働くことに不安がある方や一般企業での就労が難しい方がそれぞれの状況に合わせて働くスキルを習得したり、社会参加の機会を得たりするための支援を提供します。
- 就労継続支援A型
事業所と雇用契約を結び、最低賃金をもらいながら働く形態 - 就労継続支援B型
雇用契約を結ばず、工賃を受け取りながら軽作業などを行う形態 - 就労移行支援
一般就労を目指す方が職業訓練や就職活動のサポートを受けながら、必要なスキルや知識を習得するためのサービス
A型・B型の仕事内容については、以下の記事で詳しく紹介しています。
就労までの基本的な流れ

障害のある方が就職するまでの基本的な流れは、以下の通りです。
情報収集
まず自身の特性や希望する働き方、どのような支援が必要かなどを整理することから始めます。インターネットでの情報収集や、障害者就労に関するセミナーへの参加も有効です。
支援機関への相談
専門の支援機関に相談し具体的なサポートを受けることが重要です。
ハローワークには障害者雇用専門の窓口があり、求人情報の紹介や就職相談、職業訓練のあっせんなどを行っているほか、各市町村には相談支援センターが設置されています。一般雇用を希望する場合はハローワークへ、福祉サービスを利用した働き方を希望する場合は地域の相談支援窓口へ相談すると良いでしょう。
訓練・体験
次に、支援機関のサポートを受けながら自身の適性や興味に合わせた職業訓練や職場体験を行います。これにより実際の仕事内容や職場環境を理解し、適正を判断します。複数の職場を比較検討して、自身が働きやすい職場を探しましょう。
求人応募・面接・就職
訓練や体験を通じて準備が整ったら、支援機関から紹介された求人に応募し、面接を経て就職へと進みます。
障害者の就労で利用できる主な支援制度

障害者の就労をサポートするための様々な支援制度があります。ここでは、主要な制度について概要を解説します。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方が必要な知識や能力を習得し、就職活動を円滑に進めるための訓練やサポートを提供する福祉サービスです。職業準備訓練、職場実習、求職活動支援、職場定着支援など、多岐にわたる支援が受けられます。利用期限は、原則2年以内と定められています。
就労移行支援については、以下の記事で詳しく紹介しています。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、障害のある方が一般企業での就労を目指すために雇用契約に基づいた就労の場を提供する支援です。最低賃金が保障され、雇用保険などの社会保険にも加入できるため、安定した働き方を求める方に適しています。働き方は事業所によって異なりますが、週3〜5日程度、1日4〜6時間の就労形態が多い傾向にあります。
A型事業所については、以下の記事で詳しく紹介しています。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、一般企業での就労や就労継続支援A型での就労が難しい方が雇用契約を結ばずに軽作業などの作業を行い、工賃を受け取りながら、自身のペースで働くことができる支援です。工賃・時間給は働く日数や時間、事業所によって異なります。体調や体力に不安がある方でも、無理なく社会参加をしながら就労に向けたスキルアップを目指せます。
B型事業所については、以下の記事で詳しく紹介しています。
障害者雇用枠での求人情報の探し方
障害者雇用枠の求人情報は、主に以下の方法で探すことができます。
- ハローワーク
- 障害者専門の窓口があり、多くの障害者雇用枠の求人情報が集まっています。専門の職員が相談に乗りながら、適切な求人を紹介してくれます。
- 障害者向け転職サイト
- 昨今、さまざまな障害者専門の求人サイトが登場しており、一般の求人サイトには掲載されないような障害特性に配慮した求人情報が多数掲載されています。
- 就労移行支援事業所
- 就労移行支援事業所は、独自の求人ルートを持っていたり企業との連携があったりするため、一般には公開されていない求人情報を提供してくれる場合があります
就労後の支援と働き方
就職はゴールではなく、新たなスタートです。就職後も継続して安定した就労ができるよう、様々な支援や工夫を知っておきましょう。
就労定着支援
就職後の職場での悩みを解決し、長期的に就労を継続できるよう「就労定着支援」というサービスがあります。これは就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターなどが提供しており、定期的な面談や職場訪問を通じて、職場での困りごとや人間関係の悩みなどを相談し、解決に向けてサポートしてくれるサービスです。
労働環境の工夫
障害者が安心して働くためには、職場における労働環境の工夫が重要です。障害者本人が企業に申し出たり、支援機関を通じて調整したりするなどして、職場と良好な関係を築いていきましょう。
- 業務内容の調整
- 障害特性に合わせて、業務内容や量を調整する。
- 労働時間の調整
- フレックスタイム制の導入や短時間勤務など、柔軟な働き方を可能にする。
- 職場環境の整備
- 車椅子の利用に配慮したバリアフリー化、視覚や聴覚に障害のある方への情報提供方法の工夫など。
- コミュニケーションの配慮
- 筆談や手話通訳の利用、分かりやすい言葉での説明など。
- 通院への配慮
- 通院のための休暇取得や、勤務時間の調整など。
A型事業所・B型事業所の1日の流れ例
A型事業所やB型事業所での1日の流れは、それぞれの事業所の特色や提供する作業内容によって異なりますが、一般的には午前中に作業を行い、昼休憩を挟んで午後に再度作業を行い、終業となります。
A型事業所の仕事内容については、以下の記事で詳しく紹介しています。
【目的別】障害者の就労支援の相談先まとめ
障害者の就労に関する相談先は複数あります。自身の状況に合わせて、適切な相談先を選ぶことが大切です。
今すぐ仕事を探したい方:ハローワーク
全国のハローワークには障害のある方向けの専門援助コーナーが設置されており、障害についての専門的な知識を持った職員・相談員が情報提供や相談に対応しています。求人情報の紹介やあっせんだけでなく面接会の開催なども行っており、幅広いサポートを受けられます。早く仕事に就きたいと考えている場合は、まずハローワークで相談してみましょう。
まず訓練を受けたい方:就労移行支援事業所
就労移行支援事業所では一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、職業訓練や就職活動支援、職場定着支援など一貫したサポートを提供しています。個別の支援計画を基にきめ細やかなサポートを受けられるため、まずは仕事を体験したい方におすすめです。
自分のペースで働きたい方:就労継続支援A型・B型事業所
A型・B型事業所は、一般就労が困難な方やまずは就労経験を積みたい方が利用できる福祉サービス事業所です。作業を通じて働くスキルを身につけたり、社会参加の機会を得たりすることができます。同じ境遇の方が在籍しているので先輩の働く姿を間近で見られるほか、自分のスキルや特性を知りたい方にも適しています。
生活全般も相談したい方:障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは障害のある方の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行っています。就職に関する相談だけでなく、日常生活の悩みや健康管理、金銭管理など幅広い相談に対応してくれるのが特徴です。仕事以外のお悩みを抱えている方は、まず障害者就業・生活支援センターへ相談に行きましょう。
様々な支援を利用して、自分に合った職場を見つけよう

障害のある方の働き方は、一般就労、障害者雇用枠での就労、福祉サービスを利用した働き方など多様な選択肢があります。自身の障害特性や希望、体調などを考慮し、働きやすい職場を選ぶことが重要です。
就労に向けてはハローワークや就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど、様々な支援機関が存在しています。これらの支援を積極的に活用して、自分らしい働き方を見つけましょう。
本記事では障害者の就労に関する基本的な情報を紹介しましたが、さらに詳しい情報や具体的な事例については、関連する記事で詳しく解説しています。ぜひそちらも参考にしてください。