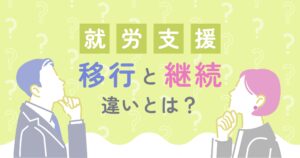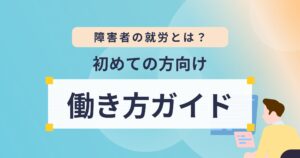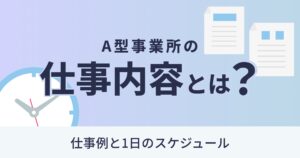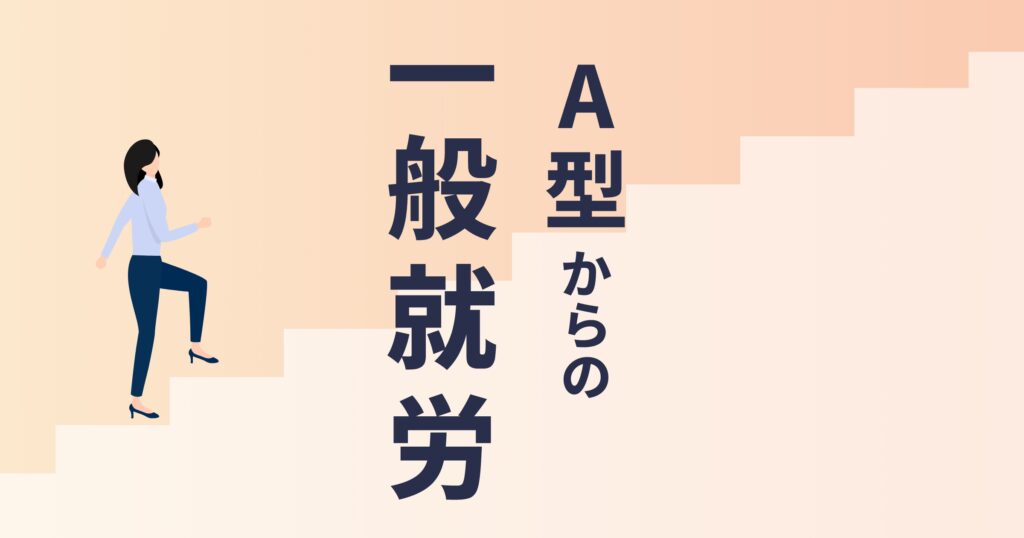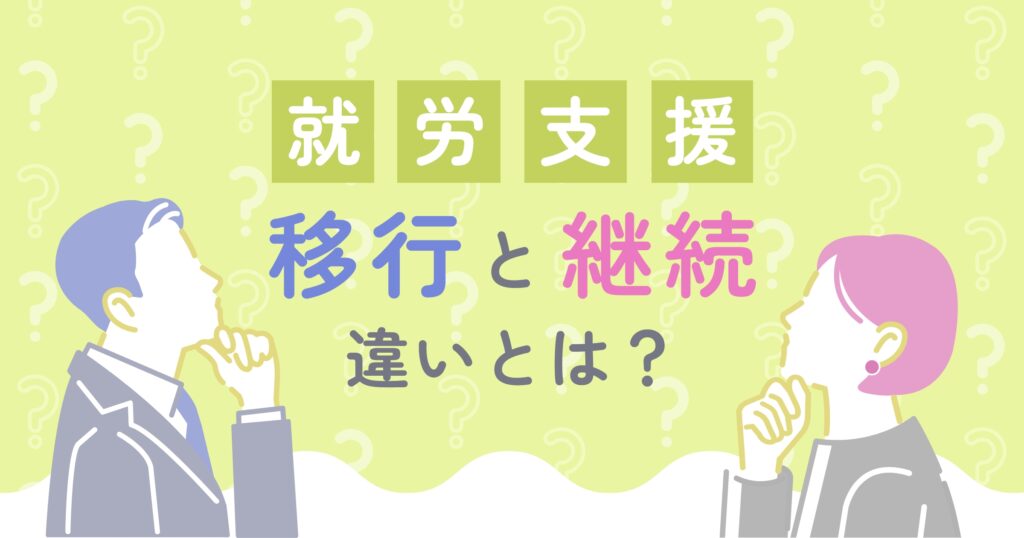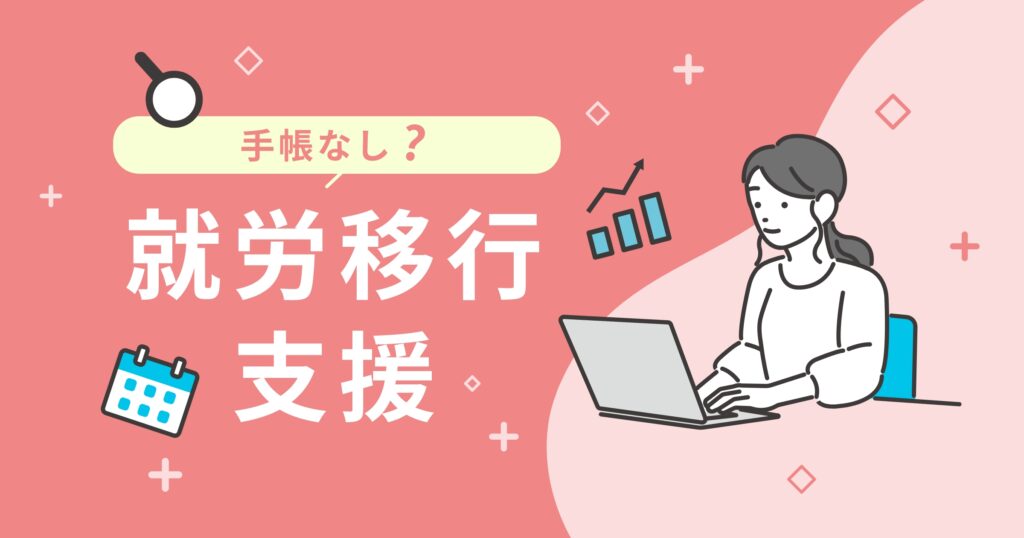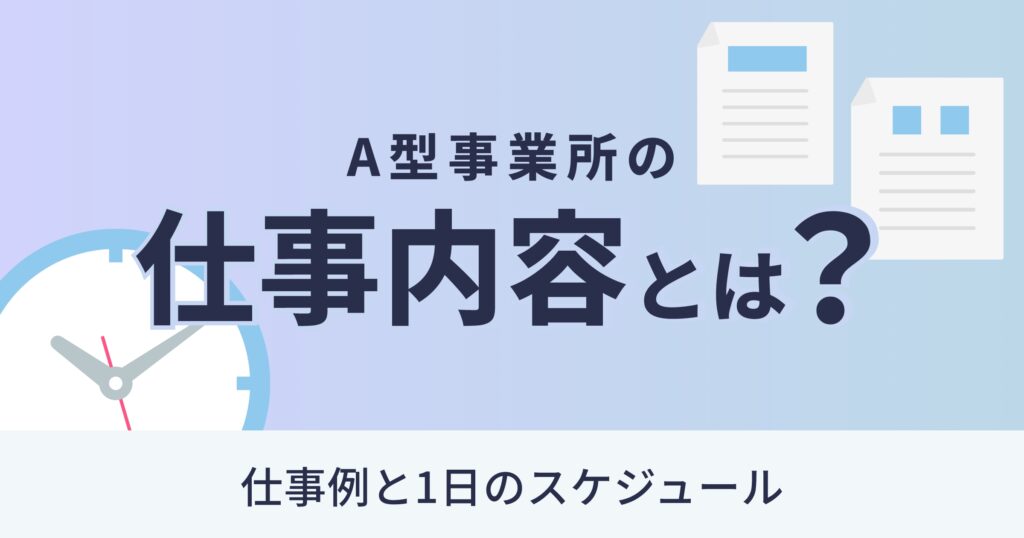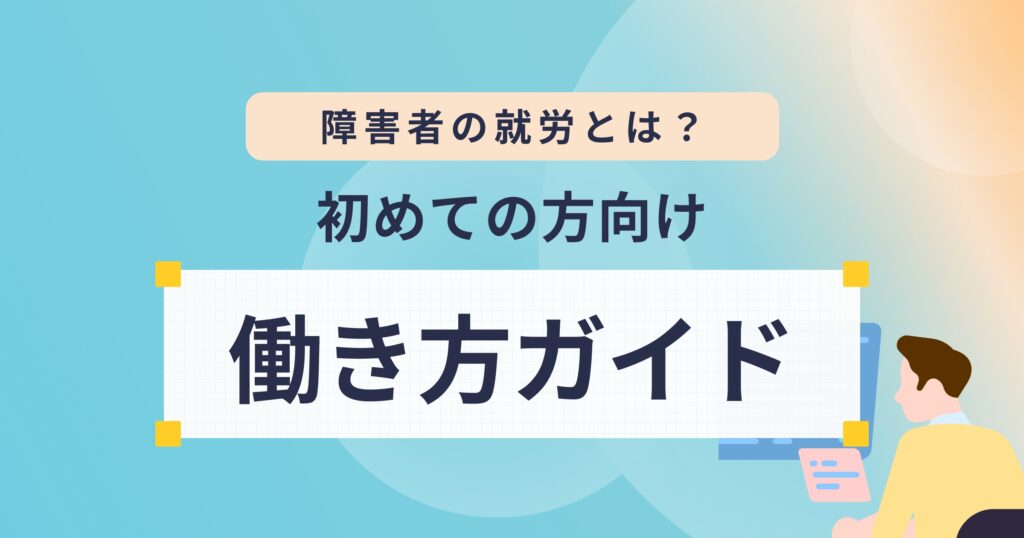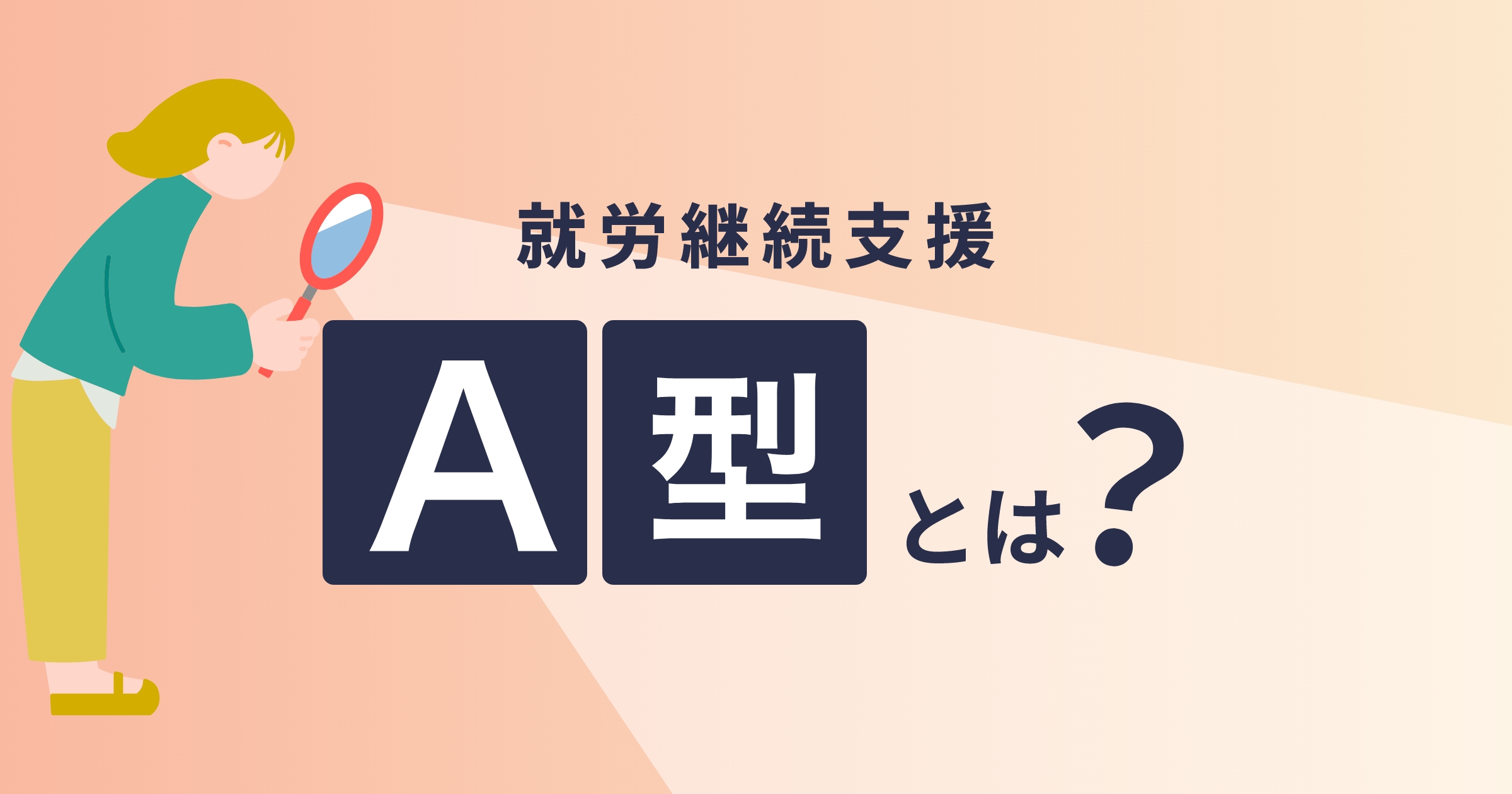
【初めての方へ】就労継続支援A型事業所とは?制度の仕組みと利用の流れ
この記事の監修者

佐井 万輝
生活支援員
高校卒業後に福祉に携わる機会があり、就労における福祉的な視点を獲得したいと考え福祉の大学に入学。卒業後はピアサポートに近い支援を行っている人材派遣会社に興味を持ち就職。その後は障害者に対して直接支援をしている就労継続支援の分野を実際に経験したいと思ったこと、また利用者の状況に応じ……
就労継続支援A型事業所とは

就労継続支援A型事業所は、障害や病気がある方が利用できる就労支援サービスです。ここではA型事業所の特徴やほかの支援サービスとの違いを説明します。
障害・病気のある方が一般企業への就職などを目指しながら働ける場所
A型事業所は、障害や病気を理由に一般企業では働くことが難しい方を対象にした、障害福祉サービスのひとつです。利用者は事業所のサポートを受けながら、個々の体調や障害の特性、スキルに合わせて働けます。
仕事内容も事業所ごとに多種多様で、自分に合った職種を選ぶことが可能です。一般企業へステップアップしたい方も、A型事業所で働きながら必要な知識を身につけたり、訓練や就職のためのサポートなどが受けられます。
障害や病気などがありながらも働きたいという方が、さまざまなサポートを受けながら安定した収入を得られる場所がA型事業所です。
雇用契約を結び、最低賃金以上の給料が支払われる
A型事業所の一番の特徴は、利用者と事業所が「雇用契約を結ぶ」ことです。雇用契約があるので労働基準法が適用され、都道府県の最低賃金以上の時給が支払われます。
また労働者としての権利が保障されているため、給料以外にも勤務時間や休日などの待遇が守られます。勤務時間の長さによっては、保険の加入が適用される場合もあります。
B型事業所・一般企業・就労移行支援との違い
B型事業所もA型事業所と同じく、障害や病気がある方が働くことのできる障害福祉サービスです。A型事業所と異なるのは、事業所と雇用契約を結ばないため最低賃金が保障されず、おこなった作業に対して「工賃」が支払われる点。体調を優先し、働く時間や作業内容に融通が利く点にも違いがあります。
就労移行支援では最大2年間で一般企業への就職を目指します。基本的に収入はなく、「働く力」を身につける場です。就職に必要な基本的なスキルや、専門的な知識の修得、職場探しや就労後の定着支援などのサポートが受けられ、体調が安定してきた方や、一般企業で働くための準備をしたい方が利用しています。
就労移行支援との違いの記事はこちら
一般企業はA型事業所と同じく、雇用契約を結び労働者として働きます。そのため最低賃金以上の安定した収入が得られ、労働者としての保障も充実しています。障害者枠で働く場合は支援を受けられることもありますが、基本的には一般社員と条件は変わりません。
就労継続支援A型事業所の制度の仕組み

A型事業所の一番の特徴は利用者が事業所と雇用契約を結んでいることです。ここではその制度の仕組みや支援制度の概要を紹介します。
利用者と事業所は雇用契約を結ぶ
利用者が事業所と「雇用契約」を結ぶことで、利用者は労働者として多くのメリットを得られます。一般企業で働くのと同じく労働基準法が適用されるため、事業所は雇用関係の書類や就業規則を作成します。条件によっては雇用保険や社会保険への加入も必要です。このように一般企業と変わらない仕組みで働きつつ、さまざまなサポートも受けられるのがA型事業所です。
最低賃金の保障・保険加入要件
「雇用契約」があることで、各都道府県の最低賃金以上の時給が保障されます。また労災保険への加入はもちろん、週20時間以上働く場合は雇用保険や健康保険などへの加入も必要です。その場合は、収入額から各保険料が引かれます。
国や自治体からの支援と利用者支援の内容
A型事業所は国や自治体が支援している福祉サービスのため、さまざまな給付金や助成金、補助金が用意されています。労働基準法が適用されるため、事業所側も一定の基準や体制を整えなければなりません。事業所は体制を整えることで国や自治体からの助成金などが受けられ、安定した運営が可能となります。
利用者は一人ひとりの特性に合わせ、以下のような支援が受けられます。
- 仕事の指導やサポート
- 仕事に必要なスキルや知識を身につけるための指導や訓練が受けられます。
- 体調面でのフォロー
- 利用者それぞれの体調に合わせて、作業時間や作業内容を相談できます。徐々に勤務時間を増やす方も多くいます。
- 生活面の相談
- 継続して働くためには体調を整えることや規則正しい生活も大切です。仕事だけでなく、日常生活の悩みや体調のことも相談できます。
- 一般企業で働くための訓練や支援
- 一般企業での就労を希望する方は、そのためのサポートが受けられます。スキルアップだけでなく、面接の練習や履歴書の作成など就職活動の支援もしています。
事業所には職業指導員、生活支援員がいるため、いつでもすぐに相談でき、仕事のことから生活のことまで幅広いサポートが受けられます。それが、一般企業で働くことが難しい人もA型事業所で安心して働ける理由です。
就労継続支援A型事業所の利用条件

「A型事業所を利用してみたいけれど、対象かどうかわからない」という方へ、ここではどのような方がA型事業所を利用できるのか、条件や利用までの流れを簡単に解説します。
利用対象者について
A型事業所を利用できるのは、障害や病気のある方で以下の項目のいずれかに当てはまる方が対象です。
- 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方
A型事業所は障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」があれば利用ができます。受給者証は障害年金証や医師の診断書などを用意し、各自治体の窓口へ申請します。用意する書類は各自治体によって違うため、お住いの障害福祉窓口に問い合わせてみましょう。
A型事業所を利用できる障害種別は以下の通りです。
- 知的障害
- 精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害など)
- 身体障害(重度身体障害以外で、軽作業が可能な方)
- 発達障害(ASD、ADHD、LDなど)
- 難病(指定難病を含む)
A型事業所は「区分1以上」といった明確な支援区分要件を設けていない場合が多いです。「区分」とは、障害福祉サービスを利用する際に必要な「支援の必要度」を数値化したものです。数字が大きいほど支援が必要とされています。
年齢や利用期間の目安
原則18歳以上65歳未満の方が対象です。65歳以上の方でも、65歳になる前に5年間サービスを利用し、65歳になる前の日までに就労継続支援A型の支給の決定を受けていれば、引き続き利用可能です。
基本的に利用期間に上限はありません。ただし、事業所の契約内容で期間が決まっている場合もありますので、事業所を探す時に利用期間の内容を確認しておきましょう。
利用開始までの基本的な流れ
A型事業所の利用は、おおまかに以下のステップで進めていきます。
- 就労継続支援A型事業所を探す
相談支援事業所などで就労についての相談をし、ハローワークや自治体の福祉課、インターネットで事業所を探します。実際に見学や体験に行き、自分に合っているかも確認しましょう。 - 「サービス等利用計画」の作成依頼
利用する事業所が見つかったら「サービス等利用計画」を作成します。作成はご自分や家族、支援相談員に依頼しましょう。 - 「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請をする
お住まいの自治体の障害福祉窓口に、障害者手帳や診断書などの必要書類を提出し、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請を行ないましょう。その後、事業所で書類選考や面接を行なった後、契約をしサービスの利用を開始します。
就労までの流れの詳しい記事はこちら
A型事業所の仕事内容と働き方の概要
仕事は各事業所ごとに違い内容も多岐にわたります。ここでは仕事内容と働き方について、簡単に解説します。
A型事業所では一般的な仕事と変わらず多種多様です。事業所によって違いますが、食品の加工や部品加工などの軽作業、接客業、パソコンを使ってのデータ入力、農作業、清掃などがあります。パソコンを使った仕事はwebデザインやプログラミングなどもあり、在宅で働ける仕事も増加中です。
勤務時間は固定されますが、どのくらい働くかどうかは相談可能です。週3〜5日の勤務が平均的ですが、週3日からスタートして徐々に増やす方が多くいます。1日あたりの労働時間は4〜6時間程度が一般的です。
利用者がどのくらい働けるかは、事業所によって異なります。体調などによって個別に時間を決める事業所もあれば、あらかじめ勤務時間が決まっている事業所もあるので、自分に合った働き方ができる事業所を探しましょう。
具体的な仕事内容例と1日の流れの詳しい記事はこちら
A型事業所の利用メリットと注意点の概要

ここでは、A型事業所のメリットやデメリットを解説します。自分に合った就労支援を見つけるためにも、就労福祉サービスの特性をしっかり把握しておきましょう。
一般就労の準備として実務経験が積める
A型事業所では実際に働きながら知識やスキルを身につけ、一般企業への就労準備もできます。さまざまな職種があるため、自分に合った仕事を探せることもメリットです。事業所でのコミュニケーションを通じて、社会人としての基本的な力も身につけられるでしょう。
雇用契約があるので最低賃金が保障される
一般企業に近い形態で働くことができ、給料が保障されているため安定した収入を得られます。仕事への意欲も高まり、社会との繋がりも感じられるでしょう。ほかにも保険など労働者としての権利が守られている点もメリットです。
サポート体制が整っている
利用者の体調や適性に合わせて、勤務時間や仕事内容を決められます。また仕事や生活面でのサポート体制も整っているので、無理のない働き方ができるでしょう。体調が整い、能力が身につけば、一般企業で働くための支援も受けられます。
A型事業所を利用するデメリット
A型事業所では雇用契約があるため、決められた時間で仕事をする体力やスキルが求められる点は注意が必要です。一般企業に近い働き方のため、仕事をやりきる責任感も求められます。体調や病気の状態によっては大変さを感じることもないとは言い切れません。
また一般企業と同じように週5日・1日8時間といったフルタイム勤務ができない点は、デメリットになる場合もあり得ます。勤務時間や仕事内容によっては、給料のみで生活費の全てを賄えない場合もある点には注意が必要です。
メリット・デメリットの詳しい比較記事はこちら