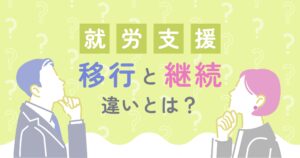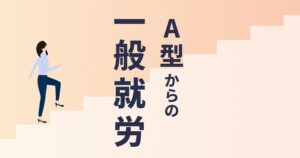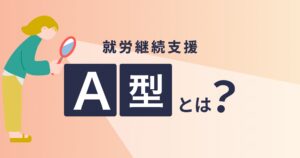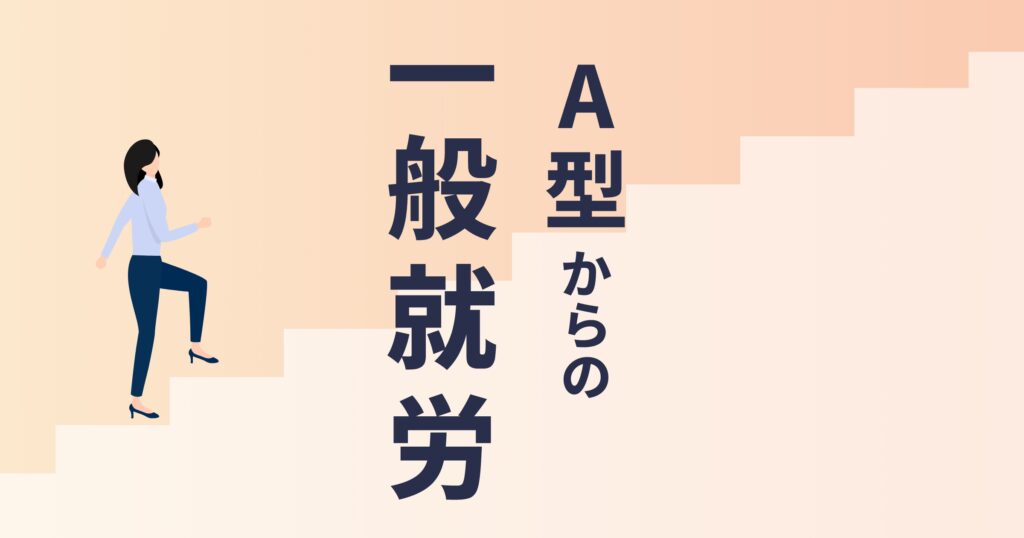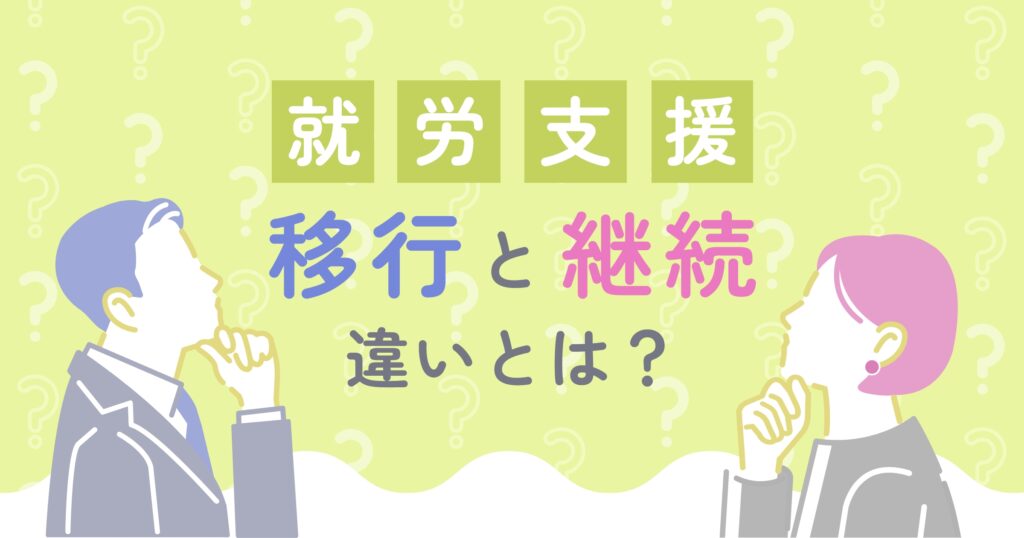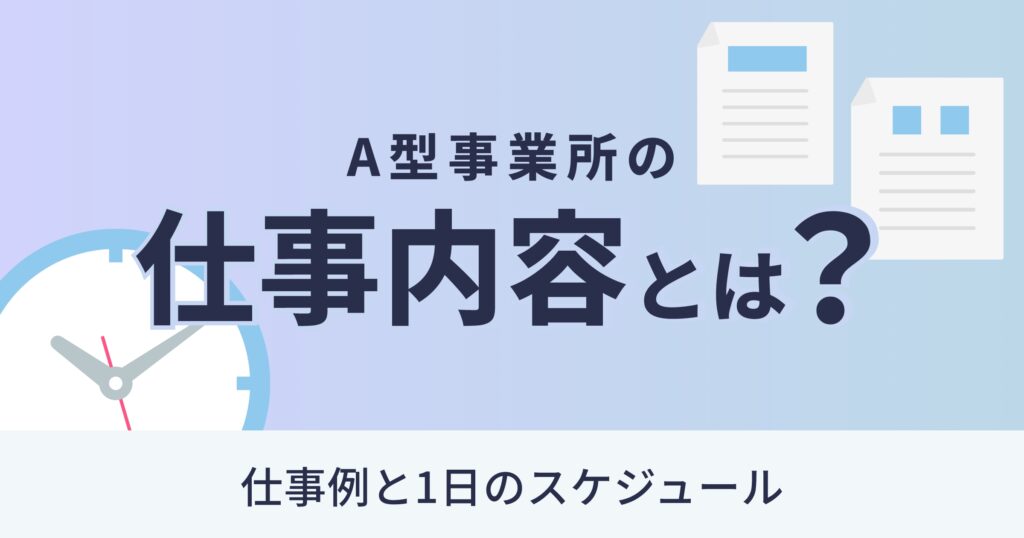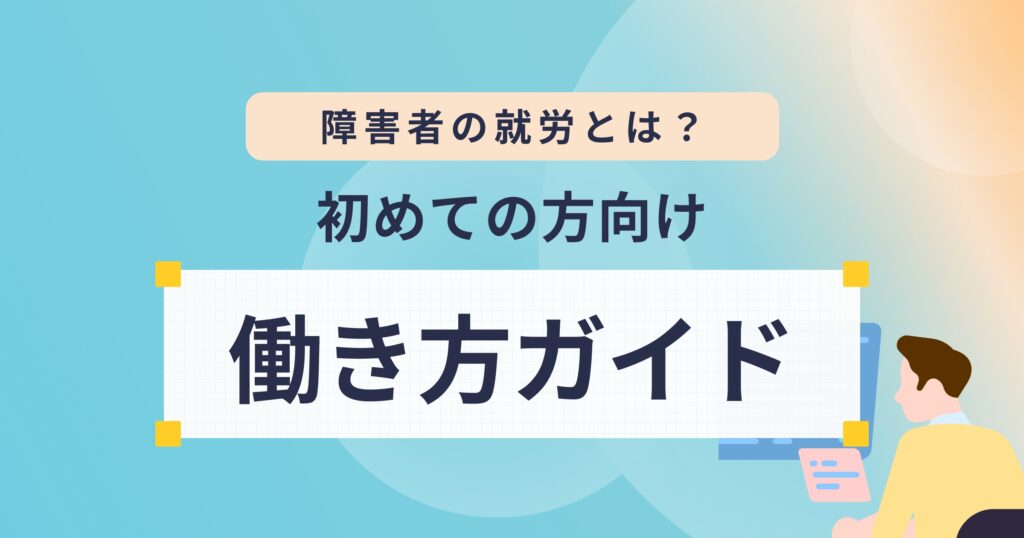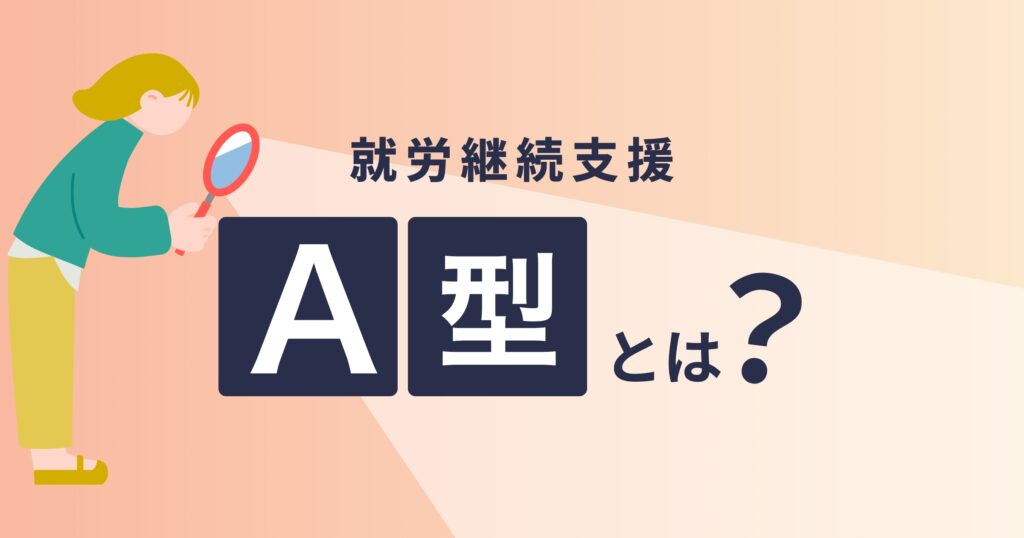就労継続支援A型は生活できない?給料実態から見据えるキャリアアップ
この記事の監修者

LEGON WORKS
株式会社絆ホールディングス
LEGON WORKS編集部は、就労継続支援A型や福祉サービス、障害福祉に関する正確で信頼性の高い情報を発信しています。 制度の解説から現場の声まで、利用者・ご家族・支援者の皆さまにとって役立つ内容を、わかりやすく丁寧に届けます。
就労継続支援A型の給料事情とは?

「就労継続支援A型事業所」は、雇用契約に基づき最低賃金以上の給与が支払われる仕組みです。B型事業所と比較すると安定した収入を得られる働き方ですが、実際のところ給料相場は地域や事業所の種類、仕事内容によって異なります。
A型事業所の平均給料と地域差
厚生労働省のデータによると、令和4年度のA型事業所の平均給料(全国)は月額86,752円でした。前年比103%と金額はアップしていますが、時給に換算すると1,000円未満。一般企業の給与と比べると、決して高いとは言えません。また最低賃金は地域によって異なるため、都市部の方が平均給与が高い傾向にあります。令和4年度の実績では、最も高額だった東京都の106,498円と、最も低額だった宮崎県の64,967円では、およそ4万円もの差がありました。
※参考:厚生労働省「令和5年度工賃(給与)の実績について」
労働時間・勤務日数の目安
A型事業所での労働時間や勤務日数は、利用者の体調や能力、事業所の規定によって様々です。フルタイムで週5日勤務するケースもありますが、一般的には週3〜5日・1日4〜6時間の勤務が多く見られます。障害特性に合わせた柔軟な働き方が可能なのがA型事業所の特徴の一つですが、その分、労働時間が短くなれば給料も少なくなるため、生活費を考慮した勤務時間・日数の選択を検討する必要があります。
一般就労との給与比較
A型事業所の給料が一般就労の給与と比べて低い理由は、A型事業所が福祉サービスの一環として利用者の就労訓練や能力向上を目的としているためです。一般企業が利益追求を主とするのに対し、A型事業所は利用者の支援に重点を置いています。柔軟なサポートがなくても問題なく働ける方やさらに収入を上げたいという方は、一般企業への就労移行も一案です。
A型事業所の給料だけで生活するのが難しい理由

前述の通り、A型事業所は一般企業と比較して給与が低いことがわかりましたが、A型事業所の収入だけで生活をしていくのは難しいのでしょうか?次に、実際にA型事業所を利用した場合の生活をシミュレーションしてみましょう。
A型事業所を利用した場合の生活シミュレーション例
【一人暮らしの場合】
| 家賃 | 5~7万円 |
|---|---|
| 食費 | 3~4万円 |
| 光熱費 | 1~1.5万円 |
| 通信費 | 0.5~1万円 |
| その他(医療費、交通費、雑費など) | 2~3万円 |
| 合計 | 11.5~16.5万円 |
A型事業所の平均月給が約8万円だとすると、一人暮らしでは毎月3.5〜8.5万円程度の赤字になる可能性があります。
【家族と同居の場合】
| 家賃 | 2~3万円 |
|---|---|
| 食費 | 1~2万円 |
| 光熱費 | 0.5~1万円 |
| 通信費 | 0.5~1万円 |
| その他(医療費、交通費、雑費など) | 1~2万円 |
| 合計 | 5~9万円 |
家族と同居の場合でも、A型事業所の月給だけでは生活費を全て賄うのは難しいですが、一人暮らしに比べて経済的な負担は軽減されます。
最低賃金基準だがフルタイム勤務が少ない現実
A型事業所では最低賃金が保障されていますが、体調面や集中力の持続など様々な理由からフルタイムでの勤務が難しいケースが多いです。結果として、短時間勤務や週数日の勤務になり、月の総支給額が少なくなってしまいます。また残業はほとんど発生しないため、残業代の上乗せも期待できません。
生活費にかかる支出と給料との差
上記シミュレーションの通り、家賃、食費、光熱費、交通費、医療費など、日常生活には様々な費用がかさみます。特に一人暮らしの場合、これらの費用は全て自己負担となるため、A型事業所の給料だけでは生活費を賄いきれないケースがほとんどです。家族と同居している場合でも、家計に占めるA型事業所の給料の割合によっては、生活費との差に悩むことがあります。
就労継続支援A型利用者を支える制度・支援まとめ
A型事業所の給料だけでは生活が難しい場合でも、様々な公的制度や支援を活用することで、経済的な安定を目指すことが可能です。
障害年金との併用
障害の状態に応じて、「障害基礎年金」や「障害厚生年金」を受給できる場合があります。障害年金は非課税所得であり、A型事業所の給料と併せて受給することで生活費の不足分を補うことができます。ただし障害年金の受給には条件があるため、年金事務所や市区町村の窓口に相談しましょう。
生活保護の併用可否と条件
A型事業所の給料と他の収入(障害年金など)を合わせても、国が定める最低生活費を下回る場合、生活保護の受給対象となる可能性があります。生活保護は最後のセーフティーネットであり、資産や能力、扶養義務者の援助など様々な条件を満たす必要があります。年齢や地域、障害の程度などによっても異なるため、お住まいの地域の福祉事務所に相談してください。
なお障害年金を受給されている方が生活保護を申請する場合、障害年金が収入認定されるため、生活保護費からその受給額が調整されます。したがって、障害年金と生活保護費の満額同時受給はできません。ただし障害年金のうち1級または2級の受給者には、生活保護費に加えて障害者加算が適用される仕組みとなっています。
「自立支援医療制度」と税金の控除減免
自立支援医療制度とは、精神疾患やてんかんなどで通院医療を受けている場合、医療費の自己負担額が軽減される制度です。通常3割負担の医療費が原則1割負担になります。
さらに障害者手帳を持っている場合、所得税や住民税の障害者控除が適用され、税負担が軽減されます。「自動車税」の減免や「相続税」の優遇措置などもあるため、申請するようにしましょう。
地方自治体の独自支援
多くの地方自治体では、障害のある方を対象とした独自の支援制度を設けています。具体的には、A型事業所への交通費助成、家賃補助、医療費助成などが挙げられます。これらの制度は自治体によって内容が異なるため、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で確認することが重要です。
生活を安定させる働き方の工夫と選択肢

A型事業所の給料と公的支援制度を組み合わせるだけでなく、自身の働き方を工夫したり、他の選択肢を検討したりすることも、生活の安定につながります。
ダブルワークや副業の可否と注意点
A型事業所での勤務時間や体調に無理がない範囲で、追加の就労を検討される方もいらっしゃいますが、必ず事前に事業所の規定を確認してください。多くの事業所では、雇用契約の性質上、ダブルワークや副業が禁止されています。また副業による収入の増加は、障害年金や生活保護といった福祉制度の受給額に影響を及ぼす可能性があります。追加の就労はご自身の収支やスケジュールを厳密に自己管理できる方に限られ、慎重な検討が必要です。
労働時間の調整・より高時給の事業所へ転職する方法
A型事業所の給料は労働時間によって変動するため、体調が安定している場合は、勤務時間を増やすことで収入アップを図れます。また現在の事業所の給料に不満がある場合は、より高時給の事業所への転職を検討することも有効です。その際は複数の事業所の情報収集を行い、自身の希望に合った条件の場所を探しましょう。
グループホームの利用・家族支援を受ける選択
一人暮らしでの経済的負担が大きい場合、障害者グループホームの利用を検討するのも良い選択肢です。グループホームは家賃や食費が抑えられるため、生活費の負担を軽減できます。また家族と同居している場合は、家族からの経済的な支援や生活面でのサポートを受けることで、生活の安定につながります。
将来のために|A型事業所からステップアップする方法

A型事業所は、一般就労に向けたステップアップの場としても活用できます。将来的な経済的自立を目指すために、以下のような方法を検討してみましょう。
就労移行支援への移行を考えるタイミング
A型事業所で一定のスキルや経験を積んだ後、より一般就労に近い形での就職を目指すのであれば、就労移行支援事業所への移行を検討するタイミングかもしれません。就労移行支援では、より専門的な就職準備訓練や履歴書作成、面接対策、職場実習など、一般就労に特化した支援を受けることができます。ただし就労移行支援は就職に関するサポートを受ける場のため、工賃が発生しない点に注意が必要です。
スキルアップ・資格取得のすすめ
A型事業所で働きながら、自身の興味や適性に合わせてスキルアップや資格取得を目指すことは、将来の選択肢を広げる上で非常に有効です。例えばパソコンスキル、簿記、介護職員初任者研修など、一般企業で役立つ資格を取得することで、就職先の選択肢が増え、より高収入の仕事に就ける可能性が高まります。
障害者雇用枠の求人探し・実例紹介
A型事業所での経験を活かし、一般企業の障害者雇用枠での就職を目指すことができます。障害者雇用枠は障害特性に配慮した働き方ができる企業が多く、安定した就労が期待できます。ハローワークや障害者専門の転職エージェントなどを活用して、積極的に求人情報を探してみましょう。
在宅ワークや自営業も選択肢に
昨今、インターネットの普及により在宅ワークの選択肢も増えています。体調の波があり、決まった時間に出勤するのが難しい方にとっては、在宅で自身のペースで働ける仕事は有効な選択肢となります。また自身のスキルや特技を活かして、小規模な自営業を始めることも可能です。これらの働き方も、将来の選択肢として検討してみる価値があります。
まとめ|A型事業所の給料事情を理解し、自分に合った働き方を選ぼう
A型事業所の給料だけで生活を維持することは、多くの場合で難しいのが現実です。しかし障害年金や生活保護、自立支援医療制度、地方自治体の独自支援など、様々な公的支援制度を有効に活用することで、経済的自立を目指すことができます。
A型事業所での経験を活かして、就労移行支援への移行や一般企業の障害者雇用枠での就職、スキルアップ、資格取得など、将来のあらゆるステップアップの選択肢を知っておくことは経済的安心感につながります。
A型事業所の利用を検討する際は、まずはお住まいの地域の障害者基幹相談支援センターやハローワークなどの支援機関に相談してみましょう。専門の支援員が、あなたの状況に合わせたアドバイスや情報提供をしてくれます。まずは気になるA型事業所の見学や体験利用をして、今後の生活を具体的にイメージすることが第一歩です。