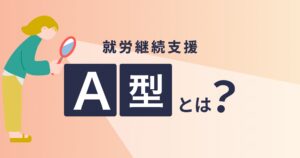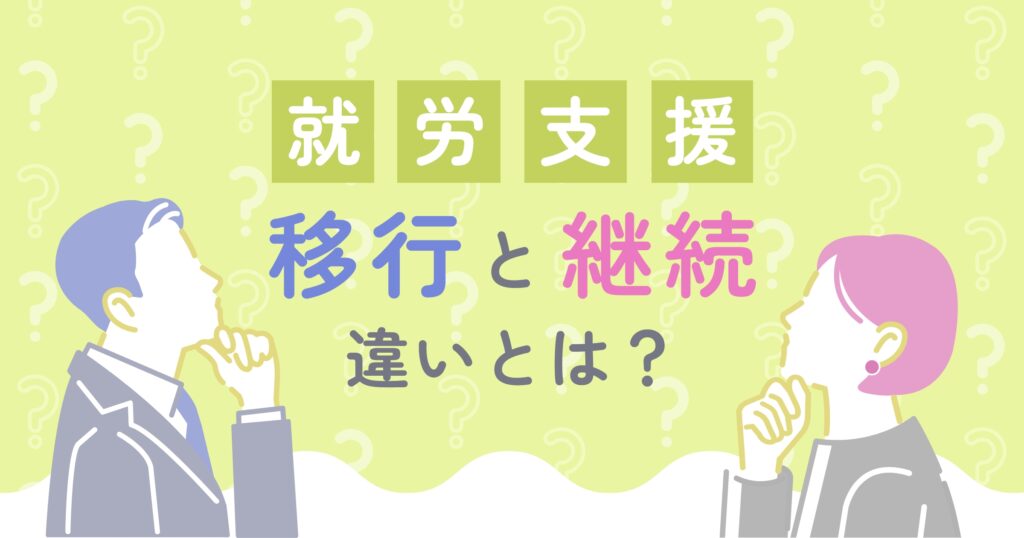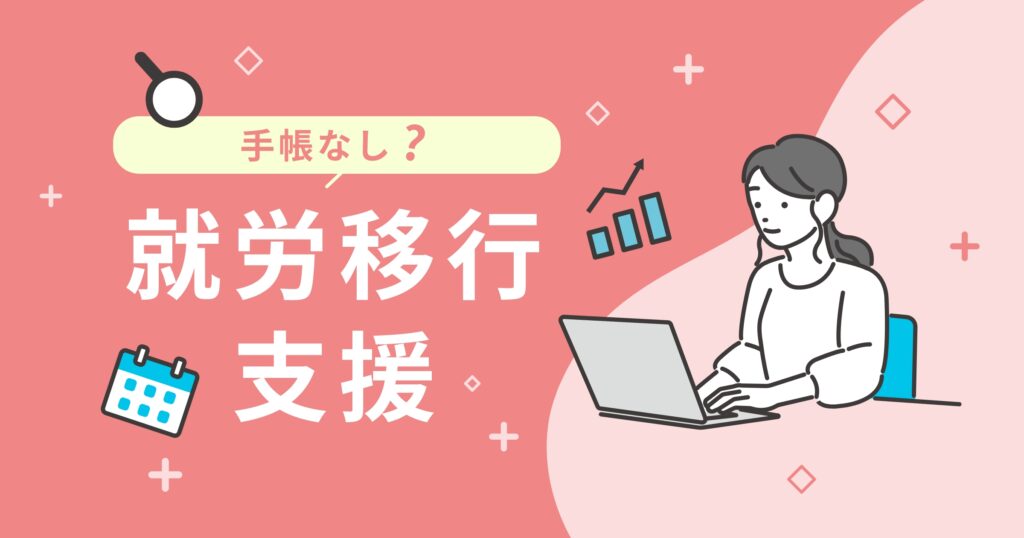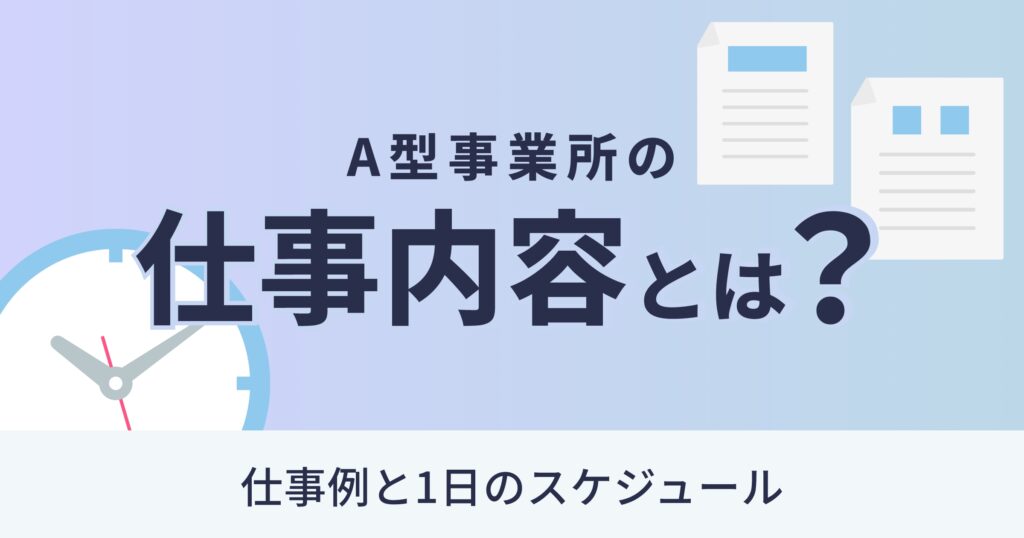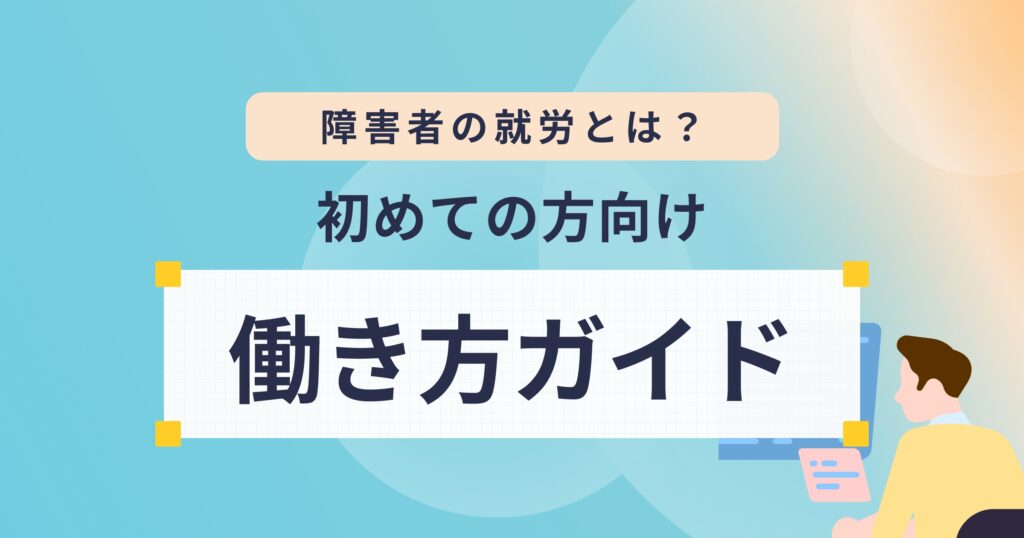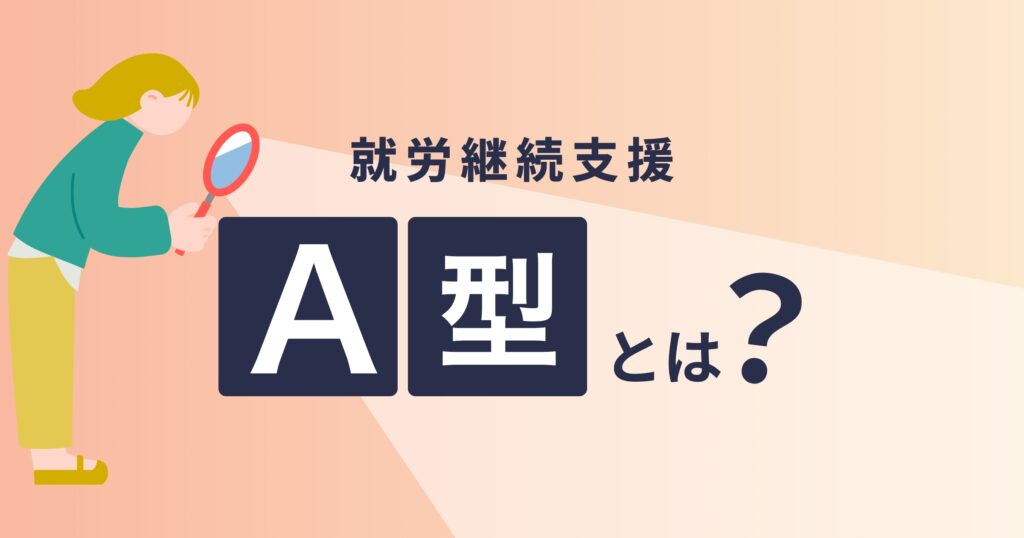【基礎解説】就労継続支援B型事業所とは?利用条件・仕事内容・向いている人
この記事の監修者

小田原 康貴
生活支援員/カウンセラー
精神科クリニックや学校現場にて、臨床心理士としてカウンセリングを行ってまいりました。 障害や精神疾患、または家庭・学校・職場などの環境により生きづらさを抱える方々のお話に耳を傾け、その方が自分らしく前を向けるよう支援を続けてきました。 なかなか理解されにくい特性を持つ方が、安……
就労継続支援B型事業所とは

障害や病気などが原因で一般企業での勤務が難しい方でも、自分のペースで働ける場所が「就労継続支援B型事業所」です。ここでは、事業所の概要や「就労継続支援A型事業所」との違い、利用するメリットなどを解説します。
福祉サービスとしての位置づけ
型事業所は、障害や病気などで一般企業で働くことが困難な方を対象にした就労系の福祉サービスのひとつです。
軽作業や働くための訓練、生活支援などをおこなっており、利用者は企業と雇用契約を結ばず、B型事業所での作業に対して「工賃」という形で収入を得られます。働く時間や仕事内容に融通が利くため、自分のペースで働ける点が最大の特徴です。
B型事業所は、利用者が体調に気をつけながら無理なく働ける場所の提供を目的としています。利用者は、通うことで社会復帰への足掛かりにもなるでしょう。
A型事業所・一般就労との違い
B型事業所とA型事業所・一般就労との大きな違いは、「直接の雇用関係があるかどうか」です。A型事業所と一般就労は事業所と雇用契約を結ぶため最低賃金が保証され、勤務時間など事業所の決まりに沿って働かなければなりません。
一方でB型事業所は雇用契約を結ばないため、最低賃金の保証対象外となりますが、利用者の体調や能力に合わせたサポートを受けながら働けるという利点があります。
利用するメリット・特徴
B型事業所のメリットは、利用者の体調や状況、症状に合わせて働ける点にあります。無理なく働けるよう働く時間や日数、作業内容を相談できるのはもちろん、事業所へ通うことになれば、生活リズムが整い日常生活も安定します。スタッフや利用者との交流を通じて、人との繋がりを感じたり孤独感が和らいだりすることもあるでしょう。多額ではありませんが工賃も得られ、働くことのやりがいも得られます。
またB型事業所の利用料は原則として1割を負担することになっていますが、公費負担が基本となり無料での利用が可能です。実際に利用者の約95%の人が無料で利用しています。
就労継続支援B型事業所の利用条件

B型事業所は、どなたでも利用できるわけではありません。ここでは、どのような方がB型事業所を利用できるのか、また申請方法などの利用までの流れをわかりやすくご紹介します。
利用できる対象者
B型事業所を利用できるのは、障害や難病を抱えており、以下の項目のいずれかに当てはまる方が対象です。
- これまでに就労経験があり、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが難しくなった方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者等によるアセスメントがおこなわれ、就労継続支援B型事業所の利用が適切であるとされた方
障害手帳をお持ちでない方でも「障害福祉サービスの受給者証」があれば利用できる場合があります。お住まいの自治体の障害福祉窓口まで問い合わせてみましょう。
年齢・障害種別・支援区分の目安
利用可能な年齢は、原則「18歳以上」です。年齢制限の上限はありませんので、高齢の方であっても利用可能です。むしろ高齢の方の利用者数は多く、令和4年12月時点の利用者分布は40歳以上の方が58.8%を占めています。
厚生労働省 就労継続支援B型に係る報酬・基準についてより
またB型事業所を利用できる障害種別は以下の通りです。
- 知的障害
- 精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害など)
- 身体障害(重度身体障害以外で、軽作業が可能な方)
- 発達障害(ASD、ADHD、LDなど)
- 高次脳機能障害
- 難病(指定難病を含む)
またB型事業所は「区分1以上」といった明確な支援区分要件を設けていない場合が多いです。「区分」とは、障害福祉サービスを利用する際に必要な「支援の必要度」を数値化したもので、数字が大きいほど支援が必要な度合いが高いとされています。
利用までの流れ(申請方法・必要書類など)
B型事業所を利用するには、事業所探しや自治体への手続きなどが必要です。主治医などに相談し、事業所の利用が必要かどうかを判断してもらうのもいいでしょう。
- 就労継続支援B型事業所を探す
まずは、インターネットで調べたり、お住まいの自治体の障害福祉窓口に相談したりしましょう。見学や体験をおこなっている事業所もあるので、気になった事業所があったら直接問い合わせます。 - 障害福祉窓口に利用申請をする
利用したい事業所が見つかったら、お住まいの障害福祉窓口で利用申請をおこないます。申請時には「サービス等利用計画書」が必要になります。こちらは相談支援員に作成を依頼したり(無料)、ご自身や家族でも作成できます。 - 事業所と契約を結び、利用を開始する
自治体から利用許可が下りると、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」が発行されます。その後、希望するB型事業所と契約をして利用が可能になります。
就労継続支援B型事業所の仕事内容
B型事業所では、自分の体調やペースに合わせて仕事ができます。ここでは、主な作業内容や1日の流れを紹介します。
主な作業内容の例
仕事内容は事業所によって違いますが、簡単な軽作業が中心になります。近年ではパソコン作業を取り入れているところもあり、事業所によって多種多様です。ご自身のできることや、興味にあった作業をしている事業所を選びましょう。
具体的には
- 内職系軽作業(シール貼り・封入・組み立てなど)
- 農作業・清掃・リサイクル作業
- 飲食物の製造・販売補助
- その他の特色ある作業(例:手芸・PC入力など
仕事の進め方・1日の流れの例
仕事については、面談などを通じて立てた個別の目標に合わせて作業内容、時間、量を決めていきます。作業の仕方はスタッフの方が丁寧に教えてくれ、困ったときにはすぐにサポートしてくれるので安心です。
事業所での過ごし方は人ぞれぞれですが、大まかな例を紹介します。
<1日の流れの例>
- 通所
- 朝礼と作業の準備
その日の体調や作業内容の確認をし、作業の準備をします。ラジオ体操などをおこなう事業所もあります。 - 午前の作業開始
それぞれの作業を始めます。こまめな休憩もOKです。午前のみや午後のみの作業の方もいらっしゃいます。 - 昼休憩・昼食
休憩をしながらお昼を食べます。スタッフやほかの利用者の方とのコミュニケーションを楽しみましょう。 - 午後の作業再開
- 片付け・終礼
掃除や片付けをし、1日の振り返りや報告をおこないます。 - 帰宅
就労継続支援B型事業所の工賃について
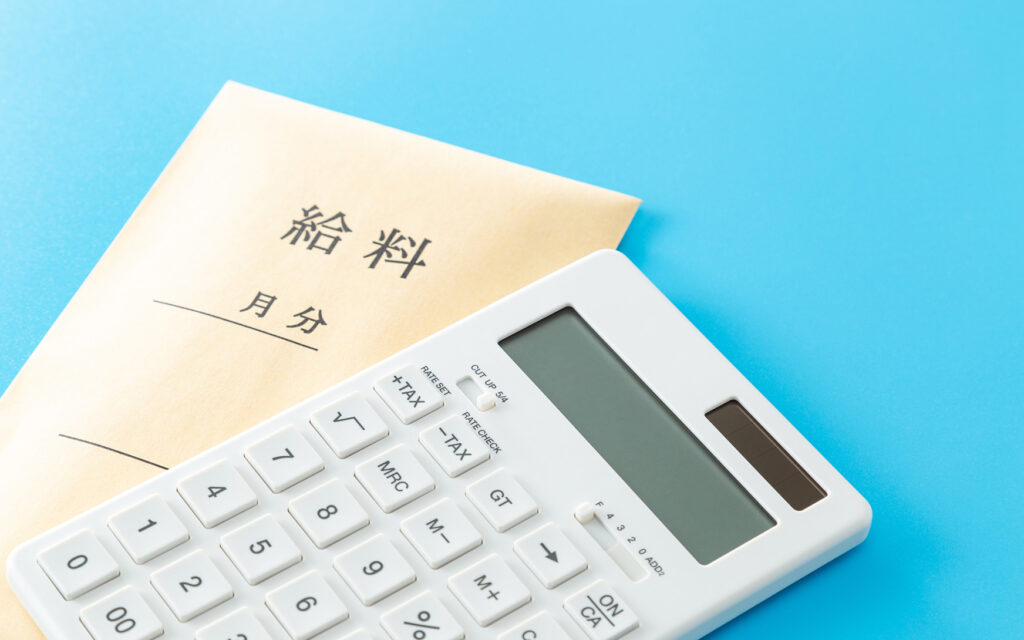
B型事業所では利用者がおこなった作業に対し支払われる報酬を、給与ではなく工賃といいます。ここでは工賃の目安や仕組み、他収入と両立できるかどうかについてご紹介します。
工賃の目安と支給の仕組み
B型事業所では、利用者がおこなった作業に対して「工賃」が支払われます。事業所と利用者の間で雇用契約がないため、一般的な「給与」と異なり「最低賃金」の適用がありません。そのため労働関係の法令が適用される給与よりも工賃額は安くなります。
工賃額は事業所や作業内容によって異なり、働く時間も人それぞれ違うため貰える金額にはばらつきがあります。工賃の支給額は、各事業所が作成した工賃額の決定方法や支払日、支払方法が書かれた「工賃規定」により決定します。また工賃は以下のいずれかの方法で支払われることを覚えておくとよいでしょう。
- 出来高制…作業した個数や作業量に応じて支払う
- 時給制…作業時間に応じて一定の時給で支払う
- 定額制…時間や量にかかわらず、日額または月額で一定額を支払う
他収入(障害年金・生活保護)との両立
事業所で貰える工賃額はそれほど多くないため、ほとんどの方は障害年金や生活保護といったほかの公的支援と併用しています。以下は、公的支援と両立するための注意点です。
- 障害年金
併用が可能です。工賃が高額になり、通常の就労が可能と判断されると更新審査に影響が出ることがあります。 - 生活保護
併用が可能です。控除制度があり、月15,000円以下であれば全額控除されます。それ以上になっても急に生活保護が打ち切られることはありません。
工賃アップを目指すには
B型事業所では作業時間や作業量によって工賃が変わります。そのためできることを増やしていくことで、工賃アップを目指すことができます。
ポイントは無理をしない範囲で少しずつ増やすこと。頑張りすぎて体調を崩してしまっては逆効果です。支援員や家族と相談しながらできる範囲で目標をたてましょう。
具体的には
- 出勤日数や作業時間を増やす
- 得意な作業をする
- 安定して通所するために体調を整える
事業所によっては、スキルアップのための勉強会やトレーニングをおこなっています。利用者がスキルアップすることで作業の幅が広がり、より工賃の高い仕事に挑戦することも可能になります。
就労継続支援B型事業所の利用に向いている人

ここでは、どのような方がB型事業所の利用に向いているのかを解説します。実際の利用者の例もご紹介しますので、参考にしてください。
向いている方の特徴
・一般就労やA型事業所の利用が難しいと感じる方
フルタイムやA型事業所のように週3〜5日働くことが難しい方は、通所日を選べるB型事業所が向いています。
- 自分のペースで働きたい方
B型事業所は働く日数や時間が調整できるので、体調に合わせて「週に1日1時間」から始められます。慣れたら日数を増やすなどもできます。 - 体調や障害の状態に波がある方
体調を優先して働けるため、重度の障害がある方や高齢の方も無理せず働くことができます。またお休みも取りやすいので安心です。
B型事業所は専門スタッフの手厚いサポート体制も特徴です。社会復帰のための一歩を踏み出したい方や、働くことで生活のリズムを整えたい方に向いています。
実際の利用者の事例・ケース紹介
パニック障害(50代女性)

週5日程度通っており、移行支援を利用していた時より、利用回数が増えました。
ハンドメイドの作品が売れたことにより自信が付いてきています。
発達障害(10代男性)

週4日程度通っています。中々集団に入れませんでしたが、作業を通して人と関われるようになってきました。
知的障害(20代女性)

週3日程度通っています。利用前はグループホームで日中、何もすることがなかったのですが、事業所利用を通して、日中の活動が充実し、できることも増えてきました。
就労継続支援B型事業所を選ぶときのポイント
全国には数多くの就労継続支援B型事業所があります。選ぶ際に一番大切なことは「自分にあった事業所を選ぶこと」です。最初からひとつに絞らず、何ヶ所か検討することをおすすめします。
また、支援する障害の対象が決まっている事業所もあります。幅広い障害の方を受け入れているのか、ひとつの障害に特化して支援している事務所なのかも知っておきましょう。
以下のポイントを参考にすると、あなたに合った事業所を選びやすくなります。
- 作業内容が合っているか
自分の興味のある仕事や、自分の体調に合った仕事ができるかを確認します。事業所ごとに仕事内容は大きく異なるため、まずはどのような作業をしているか調べてみましょう。 - 柔軟に働けるか
事業所で利用日数や時間が決まっている場合もあります。週1日から利用できるか、午前・午後だけの利用ができるかなど、働き方を細かくチェックしておきましょう。体調に合わせて作業量が柔軟に調整できるかも併せて確認します。 - 通いやすさ
身体の負担にならない距離の事業所を選ぶのが、長く続けられるポイントでもあります。事業所までの交通手段やかかる時間を確認しましょう。無料の送迎サービスや交通費の支給がある事業所もあります。 - 支援体制、事業所の雰囲気
B型事業所では就労支援のほかに日常生活のサポートや、体調の相談などをおこなっています。サポート体制の内容が充実しているかも確認しましょう。
また働くときにいつも一緒にいてくれるスタッフや、事業所の雰囲気が自分と合うかどうか確かめます。スタッフに話しかけやすいか、ほかの利用者の様子はどうか、施設は清潔かなど確認するために、事前に見学・体験に行ってみることをおすすめします。 - 工賃について
モチベーションにつながる工賃についても、月平均どのくらい貰えるのか確認してみましょう。またどのような仕組みで工賃が支払われるかも知っておくと安心です。
どの事業所がよいか迷ったときは、地域の相談員の方や福祉窓口に相談してみるのもいいでしょう。自分の体調を考慮しつつ、「何がしたいか」や「何ができるか」を考えながらあなたにぴったりな事業所を選んでください。