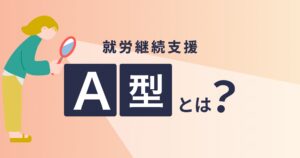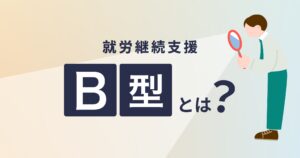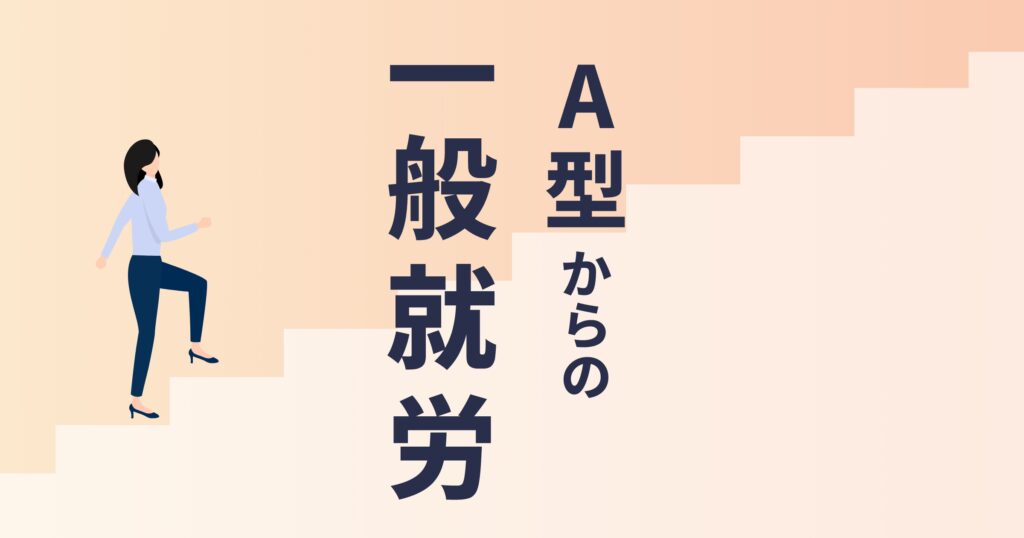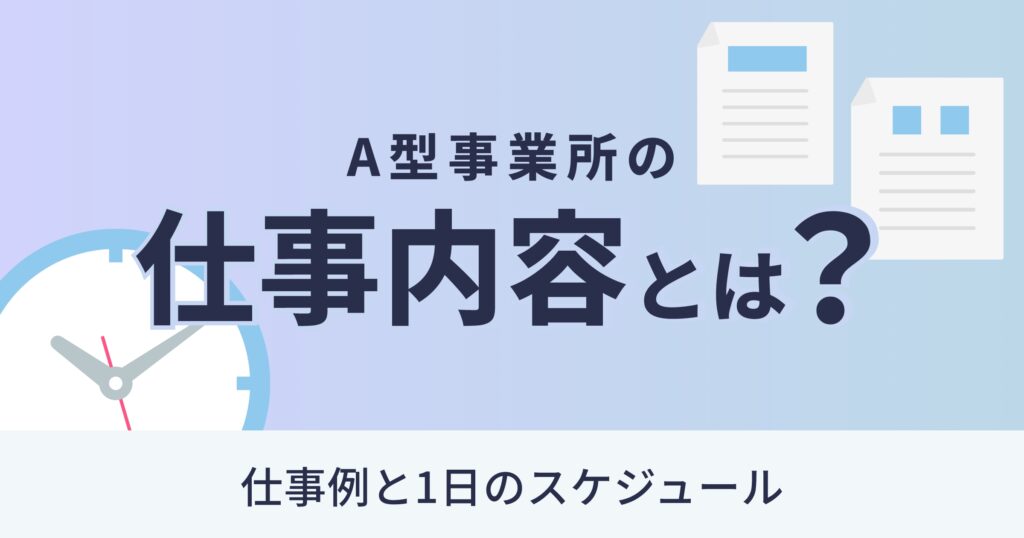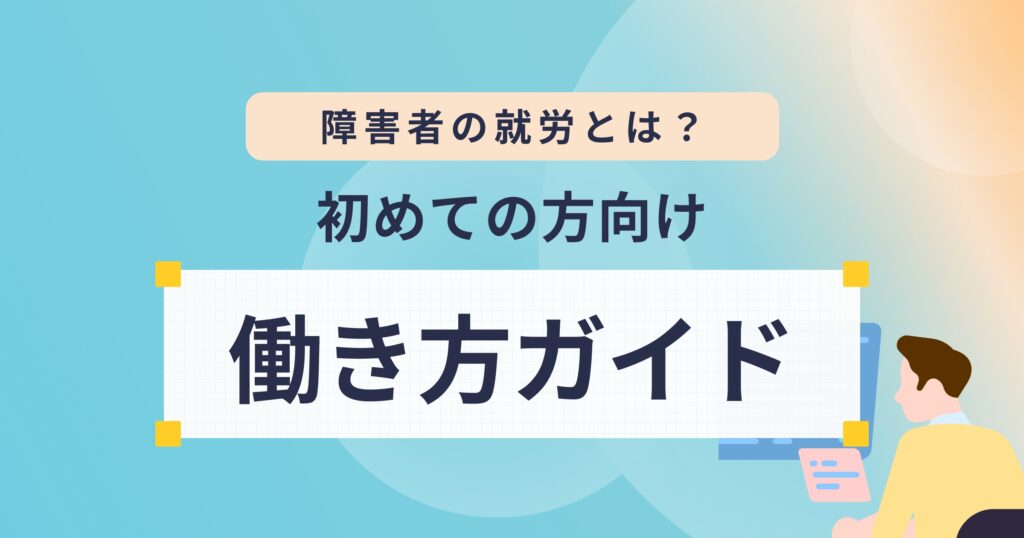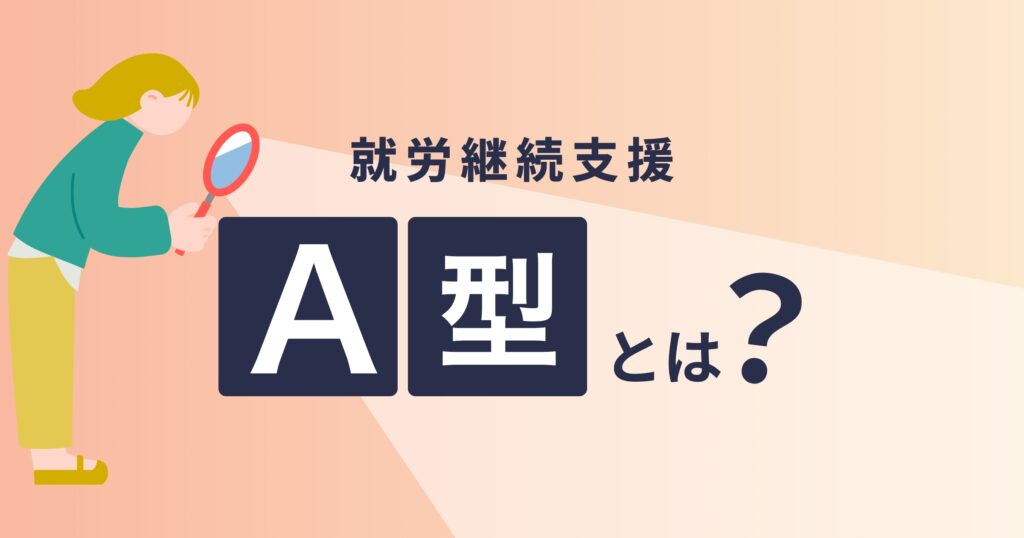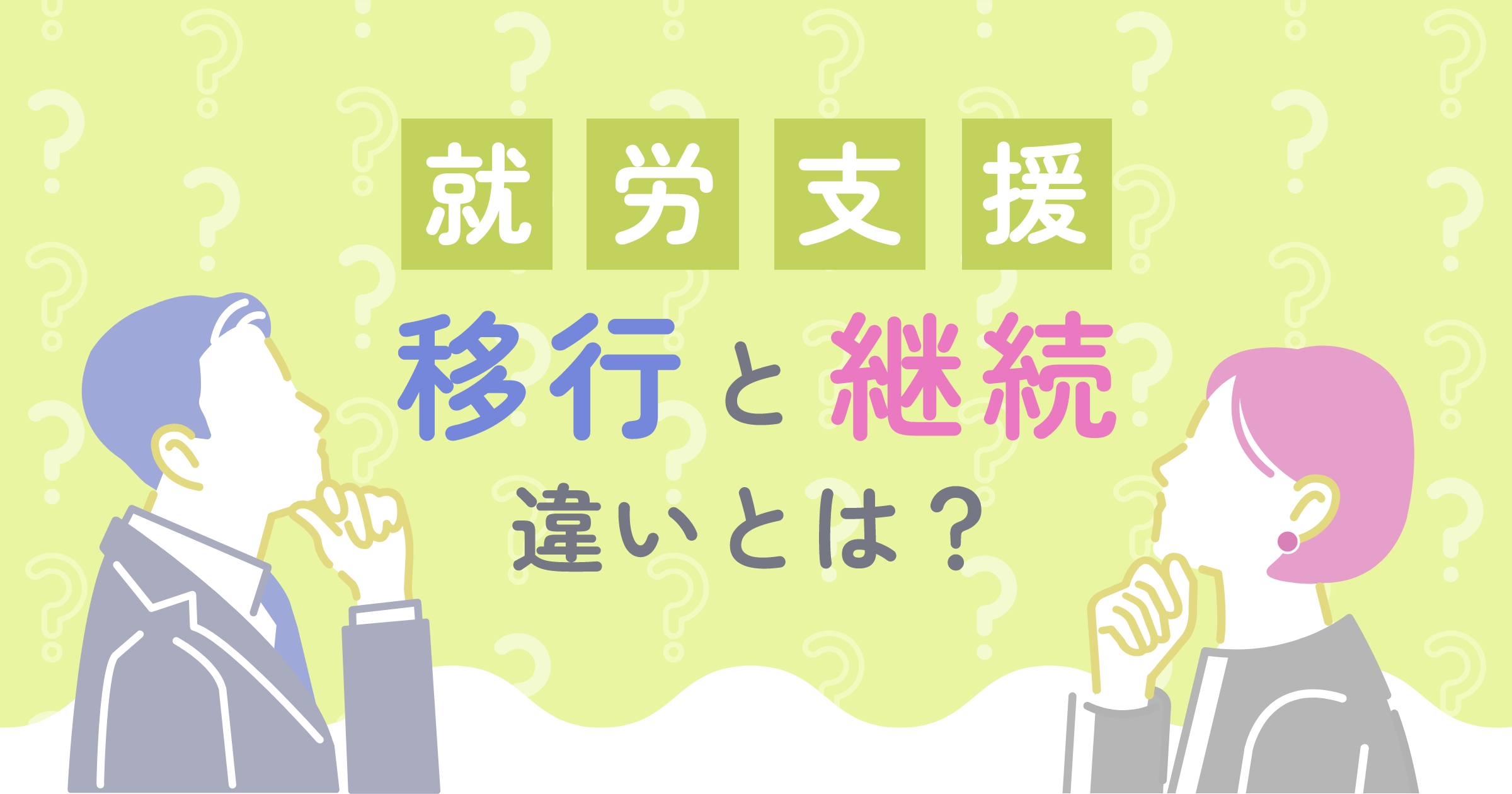
就労移行支援と就労継続支援の違いを徹底解説|目的・対象者・支援内容
この記事の監修者

小田原 康貴
生活支援員/カウンセラー
精神科クリニックや学校現場にて、臨床心理士としてカウンセリングを行ってまいりました。 障害や精神疾患、または家庭・学校・職場などの環境により生きづらさを抱える方々のお話に耳を傾け、その方が自分らしく前を向けるよう支援を続けてきました。 なかなか理解されにくい特性を持つ方が、安……
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、「一般企業への就職を目指すための支援」を提供する福祉サービスです。就職に必要な知識やスキルを習得するための訓練や、就職活動のサポート、職場定着支援などを行います。
就労移行支援の利用条件や手帳の有無については、以下の記事で詳しく解説しています。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、「長期間にわたり自分のペースで働くことを支援するサービス」です。一般企業での就労が難しい方が、それぞれの状況に合わせて働く機会を得ることを目的としています。就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があります。
就労継続支援A型事業所の詳細については、以下の記事で解説しています。
就労継続支援B型事業所の詳細については、以下の記事で解説しています。
就労移行支援と就労継続支援の違いを比較
就労移行支援と就労継続支援の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一般企業への就職 | 長期的に自分のペースで働く | 長期的に自分のペースで働く |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する障害のある方 | 一般企業での就労が困難な障害のある方 | 一般企業での就労が困難な障害のある方 |
| 年齢制限 | 65歳未満 | 65歳未満 | 制限なし |
| 支援内容 | 就職に向けた訓練、就職活動支援、職場定着支援 | 継続的な就労の機会提供、生産活動、生活支援 | 社会参加の機会提供と就労に向けた活動支援 |
| 雇用契約・賃金 | 雇用契約なし、工賃(交通費程度の支給) | 雇用契約あり、最低賃金以上の給与 | 雇用契約なし、工賃 |
| 平均月収 | ー | 86,752円(※) | 23,053円(※) |
| 利用期間 | 原則2年間(最大3年間まで延長可) | 期間の定めなし | 期間の定めなし |
<参考>利用者数の実績
| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|---|
| 利用者数(令和6年度) | 約3.6万人 | 約9万人 | 約35.3万人 |
| 一般就労への移行者数と割合(令和5年度) | 約1.6万人(58.8%) | 約5千人(26.9%) | 約5千人(11.2%) |
どちらを選ぶべき?自分に合った働き方の選び方

前述の通り、就労移行支援と就労継続支援ではそもそも目的が異なります。自身の状況やどう働きたいか、どのように社会参加していきたいか(できるか)といった目的に合わせて適切な支援を選びましょう。ここでは、それぞれの支援に向いている人の特徴を紹介します。
就労移行支援に向いている人の特徴
- 一般企業で働くことを強く希望している
就労移行支援は一般企業への就職を最終目標としているため、この目標意識が強いほど、訓練や就職活動に意欲的に取り組めます。また就職につながるスキルを実践的に学ぶ機会が豊富に提供されており、一般就労への近道と言えます。 - 就職活動の具体的なサポートを受けたい
就労移行支援事業所では履歴書添削、面接練習など専門スタッフによる就職活動支援が受けられるため、一人で就職活動を進めるのが難しいと感じている人に最適です。 - コミュニケーションスキルを向上させたい
就労移行支援事業所はビジネスマナーや身だしなみなど、社会人としての基礎知識を学べる場です。一般就労したいという意欲はあるものの、対人関係やコミュニケーションに不安を感じている人に適しています。
就労継続支援A型が向いている人
- 一般企業での就労は難しいと感じているが、働く意欲はある
A型は一般企業と比べて勤務時間こそ少ないですが、一般就労と同様に雇用契約を結んで働くため、仕事への責任感や経験を積むことができます。 - 支援を受けながら働きたい
A型は、最低賃金以上の賃金が保障されています。そのため経済的な安定を得つつ、働く習慣や職業スキルを身につけることができ、将来的な一般就労へのステップアップにつなげたい人に適しています。 - 規則正しい生活習慣があり、週5日勤務が可能
A型は雇用契約に基づき、定められた時間で働くことが求められるため、ある程度生活リズムが整っている人に適しています。働く意欲があっても体調面で不安がある人は、まずB型で慣れてからA型に移行するのも一案です。
就労継続支援B型が向いている人
- 自分のペースで無理なく働きたい、長時間の勤務や週5日勤務が難しい
B型は雇用契約を結ばないため、利用者の体調やペースに合わせて無理なく作業を継続できます。そのため、体調の波がある方でも精神的な不安やプレッシャーを抱えにくいでしょう。 - 社会とのつながりを持ちながら、生産活動に参加したい
B型は事業所での作業を通じて社会的な役割や居場所を得ることができ、マイペースに生産活動に参加することが可能です。
- 生活リズムを整えたり、体力向上を目指したりしながら、ゆっくりと次のステップを考えたい
B型は雇用契約による時間的拘束が少ないため、自身の体調や生活を立て直すことに重点を置きながら、将来の働き方を模索できるのが魅力です。生活習慣や働くリズムを整えることから始めたい人に適しています。
以下は、それぞれの作業内容の一例をまとめたものです。参考にしてください。
▼作業内容の違い(一例)
| 就労移行支援 (就労に向けたトレーニング内容) |
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|
| ・ビジネスマナー、挨拶、職場での身なりの習得 ・基礎体力や集中力の向上 ・PCや基本ソフトの習得 ・グループワーク ・面接練習 など |
・パソコンによるデータ入力代行 ・カフェやレストランのホール ・倉庫で商品の梱包や発送などの軽作業 ・工場で加工や検品 など |
・農作業 ・清掃、施設管理 ・工場で部品や機械の組み立て ・パンや菓子のなどの製造 ・お弁当の調理や盛り付け ・郵便物の封入や仕分け作業 など |
利用前に相談すべき機関・窓口の紹介

どのサービスを選ぶべきか迷う場合は、以下の支援機関・窓口に相談してみましょう。ここでは、主な相談先とそれぞれの役割や特徴を紹介します。
ハローワーク
ハローワークは厚生労働省が運営する公共職業安定所であり、就職に関するあらゆる相談を受け付けています。特に障害のある方向けには専門の窓口が設けられており、個別の就職相談や求人情報の提供、就職に向けた支援プログラムの紹介を行っています。就労移行支援や就労継続支援を含む福祉サービスに関する情報も得ることができ、これらのサービスが自身の就職活動にどのように役立つか、具体的にアドバイスを受けることができます。
また職業訓練の案内や履歴書・職務経歴書の書き方、面接対策など、就職に必要な実践的なサポートも提供しています。まずは漠然と「働きたい」と考えている場合でも、気軽に相談してみることで、就労に向けた第一歩を踏み出すきっかけとなるでしょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害のある方が職業生活を円滑に送れるよう就業面と生活面の両方から一体的な支援を行う機関です。就職に関する相談はもちろんのこと、就職後の職場での人間関係や生活習慣、金銭管理など、日常生活における幅広い悩みについても相談に乗ってくれます。
福祉支援サービスの利用に関する情報提供や、適切な事業所選びのアドバイスのほか、ハローワークと連携しながら、より総合的な視点で個々の状況に合わせた支援計画を立て、安定した就労と生活をサポートしてくれます。就労だけでなく、生活全般にわたる不安を抱えている方にとって、非常に心強い存在となるでしょう。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口は、障害福祉サービス全般に関する総合的な相談窓口です。就労移行支援や就労継続支援の利用申請を受け付け、障害福祉サービス受給者証の発行手続きを行う場所でもあります。地域の様々な障害福祉サービスに関する情報を提供しており、ご自身の状況に合ったサービスを見つけるためのアドバイスを受けることができます。
また利用料金に関する制度や、地域の他の支援機関との連携についても教えてもらえるため、地域に密着した支援情報を得るには最適な窓口です。まずは福祉サービスの全体像を知りたい、具体的な申請手続きについて知りたいといった場合に、最初に訪れるべき窓口と言えるでしょう。
福祉支援サービスを利用する際に必要なもの

就労移行支援や就労継続支援など福祉支援サービスを利用する際に必要なのが、「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証は障害福祉サービスを利用するための証明書であり、これがないとサービスを利用することはできません。
受給者証を取得するまでの一般的な手順は、以下の通りです。
相談・申請
まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所に相談し、サービス利用の意向を伝えます。そこで必要な書類や手続きについての説明を受け、申請書を提出します。
状況調査
申請後、市区町村の担当者や相談支援専門員が、現在の生活状況や障害の状況について面談を通じて聞き取りを行います。
サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所が、面談で得られた情報と本人の希望に基づき「サービス等利用計画案」を作成します。この計画案は、どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用するかを具体的に示したものです。
支給決定・受給者証の交付
市区町村は提出された申請書とサービス等利用計画案に基づき、サービスの支給を決定します。支給が決定されると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
事業所との契約
受給者証が交付されたら、利用を希望する事業所と正式に契約を結び、サービスの利用を開始できます。
この受給者証の取得には一定の時間がかかる場合があるため、サービス利用を検討し始めたら、早めに市区町村の窓口に相談することが大切です。その他、事業所によっては医師の診断書や障害者手帳の写しなどが必要となる場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
支援先は自身の目的や状況に合わせた選択を
就労移行支援と就労継続支援は、いずれも障害のある方が利用できる福祉サービスですが、それぞれ目的や支援内容が異なります。基本的には、一般企業への就職を目指す場合は就労移行支援、自分のペースで長期的に働くことを希望する場合は就労継続支援が選択肢となります。現在の体調や環境、目標に合わせて最適なサービスを選ぶために、本記事で紹介した内容やリンク先の記事を参考に、まずは専門機関に相談してみましょう。